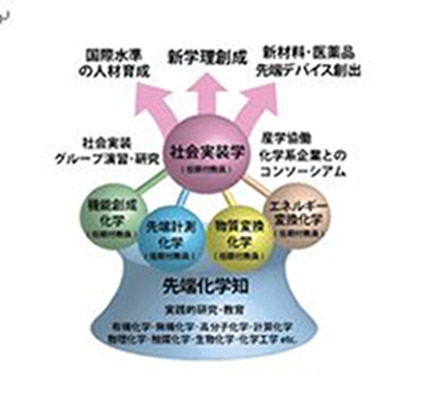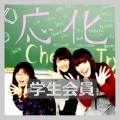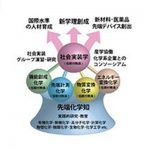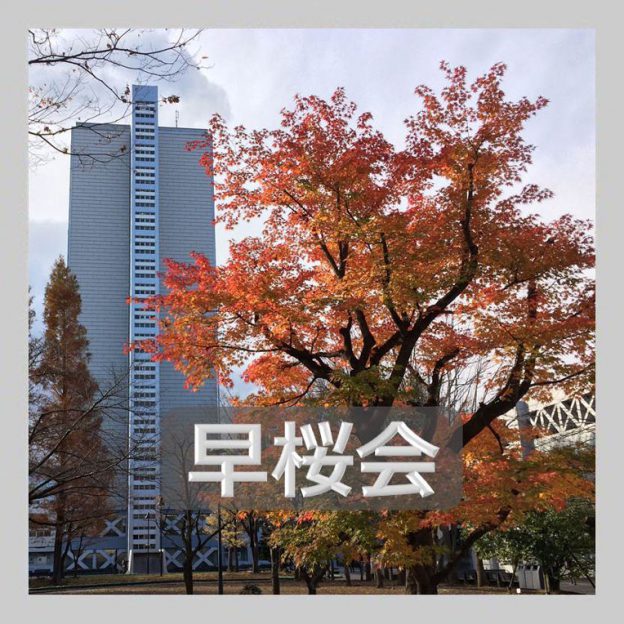応用化学科 教授 桐村 光太郎
専任講師 須賀 健雄
応用化学会 交流委員 河野 恭一
椎名 聡
関谷 紘一(記)
1.見学趣旨
大学側の教育行事として、応化学生に対し学部2年生を対象に、工場・研究所見学を催行し、企業の製造、生産管理、研究開発等の実態を学ばせ、今後の勉学への動機付を行うことを目的とします。
開催時期は夏休み中の後半の平日とし、西早稲田キャンパスから日帰りで往復可能な地区の企業事業所・工場・研究所を対象とします。
昨年は千葉君津・富津地区でしたが、今年は横浜・厚木地区を選定しました。本企画の主管は教室、交流委員は支援。見学は先生が引率、交流委員は同伴。
2.開催日時 ・9月18日(火)
07:45 西早稲田、理工キャンパス63号館ロームスクエア前集合
08:00 バスに乗車・出発
18:30 理工キャンパス帰着・解散(バス内でアンケート記入、下車時回収)
3.参加者
・応用化学科2年生 20名、引率・同伴者5名、合計25名
・引率教員 B2担任 須賀健雄専任講師(主)、桐村光太郎教授(副)
・同伴交流委員 河野恭一(新14回、元ニチレキ)、椎名聡(新36回、日本航空)、
関谷紘一(新18回、元昭和電工)
4.見学先 (横浜・厚木地区)
AM 日本たばこ産業株式会社(JT)「たばこ中央研究所」(横浜)
住所 〒227-0052 神奈川県横浜市青葉区梅が丘6-2 電話: 045-973-5611
研究内容::JTグループのたばこ事業の基礎研究を一手に担う基幹研究所
PM 日産自動車株式会社「厚木先進技術開発センター」(NATC)(厚木)
住所 〒243-0123 神奈川県厚木市森の里青山1-1 電話 046-290-0823(代表)
研究内容:自動運転の研究、EVの先行開発、研究
5.見学スケジュール
9:10 日本たばこ産業株式会社(JT)「たばこ中央研究所」近傍停車場にバス到着
9:10〜10:00 学生到着、会場誘導、見学にあたりスケジュール、注意事項等説明、休憩
10:00〜11:00 会社概要説明、研究所見学
(望月大地氏・たばこ事業本部R&D企画部 人財開発チーム)
11:10〜11:30 早稲田応化OB鈴木拓也氏(たばこ中研、新60常田研、2012生命医科・修士 常田研) より業務紹介と質疑応答
11:30〜11:55 席替え後数組に分かれ、鈴木氏を含む早稲田理工OB技術者/研究者と昼食(弁当) (参加されたOB社員:鈴木拓也(同上)、中山悠衣(たばこ中研、2013、生命医科)、
石井徹(製品評価C、2015、生命医科)、熊谷麻美(品質分析C、2015、生命医科、
以上4名、敬称略)
11:55〜12:20 同上のメンバーでのフリートーク
12:20〜12:30 クロージング、事務所前で集合記念写真撮影。
12:30 バスに誘導、乗車、日産自動車「厚木先進技術開発センター」(NATC)へ向け出発
13:10 NATC到着
13:10〜13:20 イベントルーム入室
13:20〜14:50 研究所概要説明および設備見学
(三浦 創氏・パワーレイン・EV技術開発本部 燃費/動力性能計画・PT性能統括グル
ープ主担、早稲田担当リクルーターリーダー、1993早稲田機械出身)
14:50〜15:10 日産自動車のR&Dのビジョン説明(同上)
15:10〜15:50 日産自動車のバッテリー技術開発紹介(荻原 航氏・総合研究所 先端材料研究
所主任研究員 兼 パワートレイン・EV技術開発本部 戦略企画・先行開発グループ主
担、農工大生命工学出身)
15:50〜16:00 休憩
16:00〜17:00 応化OBを含む早稲田OB社員との懇談会
学生5〜6名+OB社員1名のグループで懇談(20分で社員が席替え)
(①16:00〜16:20、②16:20〜16:40、③16:40〜17:00)
(参加されたOBを含む社員:青柳成則(新47逢坂研)、有馬(新66門間研)、宮本(門間研)、鈴木理永(新57桐村研)、真野陽子(新47西出研、応化会理事・広報委員)、福原(金属工学科)、松廣良子、有田雅晴、以上8名、敬称略)
17:00〜17:10 会議室で 記念写真撮影後バスに乗車・出発
18:30 西早稲田キャンパスに帰還、解散
6.見学後記
・JT「たばこ中央研究所」、日産自動車「厚木先進技術開発センター」とも事前に当方の学生見学の趣旨をよく理解されており、両社の今回の見学ご担当(J・T望月大地氏、日産自動車・三浦 創氏)は会社及び当該研究所の概要説明、見学解説も学部2年生に対し分かりやすい説明をされていました。
・JTたばこ中研の応化OB鈴木氏は担当業務・職務の説明に加え、大学での研究履歴及び入社後の業務履歴、公私に渡る体験談、業務における化学の重要性、入社の動機、学生時代と入社後の意識の持ち方の違い等が具体的に話され、質疑応答も活発に交わされました。学生にとっては製造に直結する研究開発部門とそこで働く技術者のあるべき姿の一端が認識出来、理解が深まったものと思われます。
・日産自動車の三浦氏、荻原氏も同社の研究開発のコンセプト、電気自動車意義と能力向上の推移、自動運転技術の推移と2020年の市街地自動運転車上市目標、リチウムイオン電池能力(セルコンパクト化、走行距離、充電速度等)向上の推移と目標値、トヨタ中心の国家プロジェクト・次世代固体電池(硫黄利用、電解液不要、10分以下の急速充電で1,000km程度の走行可目標)開発への参加等興味深い説明をされましたが、お二人とも出身学科は機械工学、生命工学であり、入社後自動運転、電気自動車、イオン、バッテリー等をゼロから勉強して業務に取り組んできた経緯の説明は、学生にも充分参考になったことと思われます。
・両社とも応化OBを含む技術系社員とのフリートーク/懇談会では社員を交えた数グループに分かれ、それぞれ公私に渡る質疑応答で活発な意見交換がなされ、学生は大いに満足されたようです。
・今回のバスの移動は、高速、一般道とも非常にスムーズで、午前、午後とも想定より30分程度早く到着したが、両社とも快く受け入れて頂き、余裕のある対応で助かりました。
・帰りのバスで学生から回収した今回の見学会のアンケート結果も、見学会については実施方法、開催時期、内容とも概ね好評であり、今後も継続を希望しております。前回のアンケートでは学生の見学希望先は企業の研究所が多かったのですが、今回は両社とも研究所であり、プレゼンされた応化OBは何れも研究職の方だったので、学生に取って企業の研究の一端が伺える良い機会になったと思います。今後の見学先の希望は総合化学、食品関係、化粧品、鉄鋼金属の順となっています。
・今回の参加学生は20名と予定の40名の半数に留まりました。、昨年36名より16名減です。今年は昨年同様3月に見学先企業工場・研究所の選定・受入可否の確認を行い、見学先、見学日の特定を5月中旬迄に行い、夏休み前に担任の先生方及び学生委員を通じB2学生に周知・募集頂いたのですが、大幅減となりました。今後教室側と想定される原因、理由等を検討し、対策を図る所存です。
以上