12月4日(土)にオンラインにて第7回学生企画フォーラムが開催されました。本会は学生が学生のために企画・運営を行うフォーラムです。
今回は富士フイルム株式会社のご協力のもと3名の社員の方にご講演いただきました。
第7回学生企画フォーラム の学生HP ⇒ 詳細はこちら


12月4日(土)にオンラインにて第7回学生企画フォーラムが開催されました。本会は学生が学生のために企画・運営を行うフォーラムです。
今回は富士フイルム株式会社のご協力のもと3名の社員の方にご講演いただきました。
第7回学生企画フォーラム の学生HP ⇒ 詳細はこちら
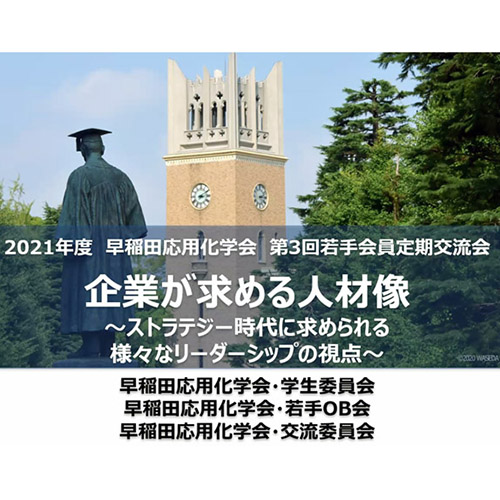

開催日 : 2021年11月20日 15:00-17:15
会場 : 西早稲田キャンパス 52-302ほか(オンライン併用)
本年より企業が求める人材像については若手会員を中心とした企画に移行している。
今回は若手会員定期交流会とのジョイントイベントということで総勢50名の参加者となった。
(内訳:B1:8名、B2:6名、B3:9名、B4:2名、M1:5名、M2:3名、卒業生10名、応化会各委員会等によるオンライン参加7名)
なお学生ホームページには学生会員からの報告が掲載されている ⇒ こちら
開会の挨拶
開会に先立ち、下村啓副会長より下記の挨拶があった。
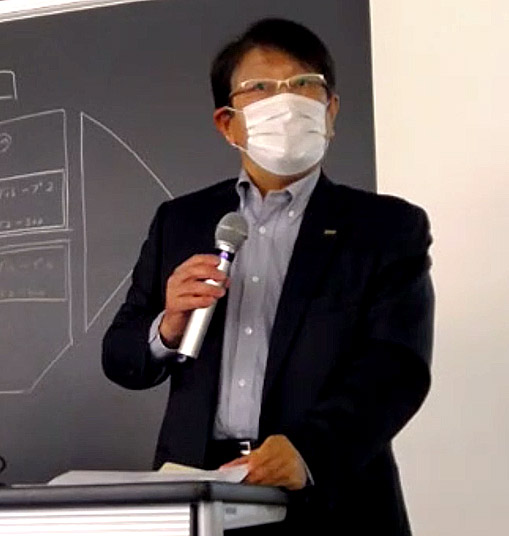
開会の挨拶 下村啓副会長
これまでに和田先生が中心になって進めてきましたこの「企業の求める人材像」の会ですが、今年は応化会の若手の皆様と学生の方々が新しい企画を考えてくれました。感謝申し上げます。
さて早稲田応用科学会は今から1年半後の2023年5月に100周年の節目を迎えます。私たちはこの100周年を機会に次世代に向けた応化会活動に多くの皆さんの力を結集させようとしています。
次の100年に向け応化会が早稲田大学はもとより、日本・世界の発展に貢献する活動を行い、その活動と共に会員の皆さんの参画が呼び起こさせるようにしたい。
この次世代に向けた応化会活動には今日ここに参加されている若手会員、学生の皆さんの行動が不可欠です。次世代のあるべき姿を指し示すのは皆さまであろう、又そうあるべきだと思います。本日の会もそのような趣旨に沿ったものと思います私たちは皆様の活動を支援しつつともに次の世代に進んでいきたいと考えています。今日の会の取り組みが次世代への第一歩となることを祈念して私の挨拶といたします。
テーマ:ストラテジー時代に求められる様々なリーダーシップの視点
イントロダクション
リーダーシップ論について劉 雲龍さん(新56、酒井・小堀研。三菱ケミカル株式会社、早稲田大学大学院商学研究科・博士後期課程商学専攻)より、説明があった.
今回のワークショップの前提としてリーダーシップとして持っているイメージをキーワードからピックアップしてディスカッションにつなげている。リーダーシップに関して画一的な正解は存在しないため、種々のリーダーシップについての考え方を共有、議論することで理解を深めることが出来るが、共通項として周囲との「関係性」重視であることがあげられる。
リーダーシップ論については、1940年代から米国などで論じられており、1990年代以降は、変化、影響、動機づけの3要素を兼ね備えるなどの提示もされているが、学術的な定義は未だに完全には定まっておらず、時代とともに変化し、進化していることをその研究の変遷とともに説明があった。
早稲田大学においても、卒業生が様々なリーダーシップモデルや、リーダーシップに関する持論等を提唱しているが、リーダーシップを発揮する行動規範として目標設定・共有、率先垂範、相互支援を通じたリーダーシップを発揮するための必要な要素についても言及された。
ワークショップ
今回のワークショップ参加者に対して事前に自己分析を実施した。コントローラー型、プロモーター型、アナライザー型、サポーター型にそれぞれカテゴリー分けし(以下参照)、以下のテーマについてOBチームも含めて5グループにてディスカッションを行った。
グループ内での議論に際し、参加者それぞれに役割分担を設定しそれぞれのスタイルでのリーダーシップを体感できるように配慮されている:
リーダーシップスタイル:
先駆者スタイル:チームの成果を高めるために、他の人 に取ってほしい行動をまず自分が取る、また、まわりから批判されそうなアイディアでも提案してみる
司会者スタイル:チームメンバーに話しを振ることでチームメンバーのアイディアを引き出し、話してもらうことでメンバーの 魅力を引き出す
航海士スタイル:チームの議論の方向性を決め、議論が脱線した場合に話しを戻す
補強者スタイル:チームが必要とする支援を行い、地味ではあっても重要なサポート役を担う
応援者スタイル:チームメンバーを精神的に支援、そのたゆまぬ努力を積極的に応援する
提案者スタイル:議論に必要と思えるアイディアを積極的に出し、成果に近づくように様々な視点から提案を行う
議論した内容はパワーポイント(最大5枚)に纏め、各グループの持ち時間6分の中で3分説明、2分質疑応答、1分纏め・振り返りの役割分担を設定した上でプレゼンテーションするスタイルを取り参加者全員に対して共有を行った。
参加者からは「環境問題について」応化会関係者に限定せず、環境省などのプロフェショナル領域から広く講師を招聘して充実した議論を実施する、「将来設計」としての社会保障や資産形成などについてのナレッジインプット、「就職活動に向けた講義」として進路決定の様々な選択肢に対して企業の取り組みや交渉術などそれぞれ有用な知見を共有して頂く、「化学業界におけるデータサイエンスの活用」としてあらゆる文化でDX活用の事例としてビッグデータの取り扱いと具体的な化学領域への反映について、など様々な検討内容が紹介された。
まとめ
劉さんから早稲田大学と東京工業大学におけるディプロマポリシーの紹介および実行軸・思考軸を基調とした将来設計(1枚の未来地図)をを作っていったらどうかとの提案があった。今回はSTEP1として目標設定をテーマとしてグループワークし、次はSTEP2としての自己認識について理解を深めていければよいと考えている。
また、戦略力についてもあわせて説明があり、方法論としての戦略力ではなく自己にその力を付けるために道筋として備えておくべき力について紹介があった。
今回のグループワークについて最後に北村さん(B1)より、自分の気がつかない能力の使い分けの必要性と経験知の必要性、自主性とメタ認知についても意識の重要性を認識したとの感想が述べられた。
開会の挨拶
橋本副会長より以下の閉会の挨拶があった。
充実したディスカッションが出来ていた様に思います。リーダーシップは必ずしもチームだけでなく自分自身のマネジメントにおいても重要です。自分の実現すべき姿(Vision)、使命(Mission)や大切にする事(Value)を設定して自分をリードすることがまず出発点です。自分自身に対する優れたリーダーは、チームや組織においても優れたリーダーになります。特に海外の人がメンバーのチームをリードするような場合には、日本人同士のような阿吽の呼吸が効かないので、初めにチームとしてのこの三つ(Vision,Mission,Value)をクリアにして明示的に共有し、問題が起こった時にはここに立ち帰ってすり合わせをして、メンバーの納得のもとでチームをリードすることが必要です。これから海外を含めリーダーシップを発揮して活躍する機会の多い若い人たちには是非これを意識して頑張っていただきたいと思います。この企画を計画し実現させて下さった学生委員会、若手部会の皆様に感謝致します。
今回の企画開催にあたり対応された事務局メンバー:
B1:磯貝、北村、B2:石崎、内藤、B3:近藤、高田、佐々木(淳)、B4:岡、M1:西尾、本村、LD2:疋野
卒業生:神守(新69)、政本(新68)、尾崎(新65)、大山(新64)、清川(新63)、守屋(新57)、劉(新56)
(報告:学生広報班、広報委員会 加来恭彦(新39))

第17回交流講演会を2021年11月13日(土)「ウインクあいち」にて開催しました。 最初に友野支部長より、中部支部の講演依頼に対してご快諾いただいた黒田一幸名誉教授への感謝の言葉と、先生のご略歴の紹介がありました。
黒田先生の講演「ナノ空間物質の化学」の要旨
ナノ空間物質の一つであるメソポーラスシリカは、孔径2-50nmの細孔が規則正しく並んだ多孔質シリカである。 一般の合成法としては界面活性剤のミセルを鋳型としてシリカを合成し、その後の焼成により有機物を除去することで、均一な細孔径のメソポーラスシリカが得られる。
我々には、加藤忠蔵研究室から受け継いだ、材料の熱分析技術があったため、世界に先駆けて層状ケイ酸塩からのメソポーラスシリカ合成法を発見し、その論文を発表することができた。 その後、1992年に発表された米国モービル社のメソポーラスシリカに関する重要な論文には我々の1990年の論文が引用されている。
メソポーラスシリカのナノ空間は、吸着材、触媒担体などの反応場のみならず医療、分離、エネルギー分野にも有用であると考えられる。
我々が発見した当時は数えるほどだったメソポーラス材料に関する論文は、いまでは世界で年間9000件も発表されている。
SDGsには、マテリアルの革新が不可欠である。 有機物と無機物の複合化というこれまでのハイブリッド材料だけでなく、空間の設計という概念を加えた新たな「ハイブリッド材料」が役に立つに違いない。
先生のユーモアあふれる興味深いお話を、参加者一同熱心に拝聴しました。 思い通りの実験結果が得られなくとも、「できませんでした」だけではだめで、何がどうなったかを考えることが重要だ、という先生のお言葉が印象に残りました。
 黒田先生は、2021年より日本セラミックス協会の会長に就任されたそうです。 ご講演後、技術的な内容に加え現在の先生のライフスタイルに関する質問にも丁寧にお答えいただけました。
黒田先生は、2021年より日本セラミックス協会の会長に就任されたそうです。 ご講演後、技術的な内容に加え現在の先生のライフスタイルに関する質問にも丁寧にお答えいただけました。
コロナ感染防止のため、恒例の懇親会は開けませんでしたが、本当に久しぶりに対面で交流でき、参加者には満足していただけました。 その後、集合写真を撮り、研究室出身の山本理事から先生への謝辞と締めの挨拶でお開きとなりました。
参加者26名(敬称略)
堤正之(17回)、三島邦男(17回)、柿野滋(19回)、小林俊夫(19回)、友野博美(22回)、黒田一幸(24回)、木内一壽(24回)、浜名良三(29回)、鳥居良彦(29回)、服部雅幸(32回)、上宮成之(35回)、北岡諭(36回)、新村多加也(39回)、加藤克久(40回)、大高康裕(41回)、木村辰雄(44回)、浦田千尋(56回)、若林隆太郎(58回)、大西健太(62回)、山本瑛祐(63回)、永田皓也(64回)、斎藤翔平(64回)、村松佳祐(66回)、森ゆきの(66回)、山口真悠(67回)、齋藤由実(69回)
(文責 服部)
黒田先生の御略歴:
1974年早稲田大学理工学部応用化学科卒(新24回)
1979年同大学院博士課程修了工学博士(早稲田大学)
同年早大理工学部助手
1980-1981年 British Council Scholarship(英国アバディーン大学)、
1982年同専任講師
1984年同助教授
1989年同教授
2004年理工学術院教授、
2008-2010年ストックホルム大学, Affiliated Professor
2013年Ecole NormaleSupérieure de Chimie de Montpellier, Invited Professor
2017年パリ第6大学 Invited Professor
その他:
早稲田大学環境保全センター所長7年間
早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構長
東大をはじめとする多数の国立大学の非常勤講師歴任
国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の研究主幹、研究総括ほか
日本学術振興会 学術システム研究センター専門委員
日本化学会理事、同関東支部長、同筆頭副会長
日本セラミックス協会理事、同副会長、2021年 6月より会長
日本化学連合副会長
International Mesostructured Materials Association会長
ゼオライト学会会長、日本粘土学会会長、日本ゾルゲル学会会長、私立大学環境保全協議会会長等歴任
受賞等:
1996年日本粘土学会賞、
2007年日本セラミックス協会学術賞・同論文賞、
2013年文部科学大臣表彰(研究部門)、
2013年錯体化学会貢献賞、
2015年日本化学会賞、
2015年Life Time Achievement Award(IMMA)、
2019年日本セラミックス協会フェロー表彰
2019年 Life Achievement Award (International Sol Gel Society (ISGS))、
2019年 ISGS Fellow、
2019年大隈記念学術賞
以上

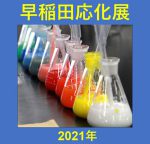 2021年11月16日から17日に掛けて対面式では2年ぶりになる早稲田理工展・応化展が開催されました。感染拡大防止の観点から入場制限を設定しながらの理工展・応化展になりましたが多くの来場者を得て盛況な理工展になっていました。
2021年11月16日から17日に掛けて対面式では2年ぶりになる早稲田理工展・応化展が開催されました。感染拡大防止の観点から入場制限を設定しながらの理工展・応化展になりましたが多くの来場者を得て盛況な理工展になっていました。
例年、応化展は実験班、展示班、屋台班の3本立てで活動しているそうですが、今年は屋台班の活動は取りやめになり実験実演と展示の2本立てで開催されました。
実験班
56号館502実験室にて以下の4タイプの実験実演を実施しました。
【1】ケミカルライト
市販のケミカルライトにも使用されている蛍光色素であるローダミンBとエオシンYを使った実演を行っていました。病理診断のための組織染色にも応用される色素ですが、視覚的には暗所における発光実験は来場者に対するインパクトがあったと思います。基底状態と励起状態の分かりにくい説明も丁寧に来場者に対してされていました。
【2】色付きクリスタルグラス
塩化コバルトや塩酸銅の結晶の色とクリスタルガラスに取り込んだ際の色の変化を含めた説明と実演と実施していました。来場者が直接加熱したガラスに触れることが出来ないため説明が多めの実演ではありますが色付きガラスの原理について来場者に分かりやすく説明をされていました。
【3】人工イクラでスノードームを作ろう
アルギン酸ナトリウム水溶液におけるカルシウムとのイオン交換によりアルギン酸が凝集する性質を使い、アルギン酸ナトリウム水溶液にあらかじめ加えてあった色素をゲルに着色させることで人工イクラを合成する実験、実演ですが用意されている色のバラエティが多く、見た目にも華やかな展示となっていました。
【4】芳香剤を作ろう
吸水性高分子であるポリアクリル酸に香料を添加した水溶液を加えることでゲルに香料を保持させる実験、展示では何種類もの香料が展示されており、水溶液を着色することで視覚にも嗅覚にも訴えることが出来るバラエティに富んだ実演が行われていました。生活用品を中心として幅広く使われている吸水性高分子について実験担当の学部生が実験書を読み込んで理解した内容の説明も熱量を感じました。
初日は午前中に一日分の整理券を配布してしまったため、午前の遅くからゆっくり来場された方は既に一日分の整理券を配布し終えている状況でしたが2日目には午前の分と午後の分の切り分けを実施したため来場者の待ち時間の改善が見られました。理工展における実演展示の多くは応化会によるものだったため、来場者の注目度も高かったように思いました。
展示班
53-204教室にて応用化学科の紹介として実施されました。
実験展示の人気が高かったことから人数調整の関係で実演に参加出来なかった来場者に対して、展示班は有機溶媒を一切使わない水道水を使った実演が可能な界面活性剤の応用によるシャボン玉の展示及び実験班でも扱っていた吸水性高分子の実演を行い多くの小中学生を含む来場者が学部生の指導のもと実験器具に触れることが出来ていました。
その他に学科の紹介として研究室での研究テーマ、学部生が使用している物理化学や実験指導書、実験ノートの展示及び応用化学科のカリキュラムに周期律表に記載されている各元素の視覚的特徴や性質などが詳述されている資料の展示など盛りだくさんで、久々の応化展で活気がまた戻ってきた印象を受けました。
学生委員会からも報告も投稿されています。学生委員会からの記事も参照ください。
広報・加来恭彦(新39)
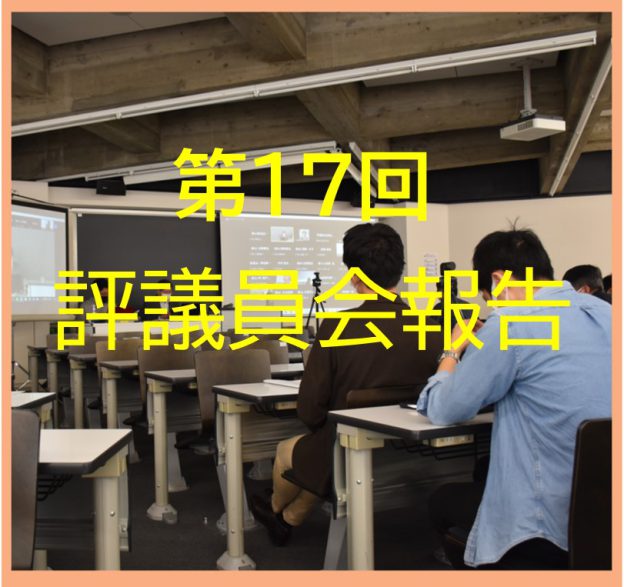
第17回評議員会が2021年10月30日(土)14時より開催されました。コロナの感染状況も落ち着いてきたため、リアル会場+オンラインのハイブリッドで行い、評議員・関係者含めリアル39名、オンライン49名の計88名が出席されました。議長は西出先生です。
門間副会長よりコロナ禍での大学の様子ご報告
会議に先立ち、門間副会長より、大学でのワクチン接種の状況、コロナ禍でも密を避ける・回数を減らす工夫をして実験授業を行っていること、課外活動が再開されたことなどが紹介されました。
濱会長挨拶
昨年からのコロナ感染状況も落ち着いてきて、リアル出席も含めて新10回から新74回まで約60世代の評議員にご参加いただいたことへの感謝をまず述べられ、先日のホームカミングデーで話のありました「なつかしい早稲田、新しいWASEDA」のように応化会もなつかしいメンバーによる強い結束と新たなつながりを通じて、沢山の人材を輩出し、世界に輝くイノベーションにつながることを期待し、評議員にはご支援いただきたい旨を述べられました。
3つの活動基本方針ごとに活動状況を報告
3つの活動基本方針に沿って、各委員長、支部代表、活動中心メンバーよりアクティビティの報告がありました。
椎名交流委員長からは、「交流会講演会」、「先輩からのメッセージ」、今年始まった博士人材の輩出支援の「先輩博士からのメッセージ」などの実績・今後の計画を、佐藤広報委員長からは、先生・卒業生へのインタビュー企画、ホームページの外注化検討が進んでいること、梅澤基盤委員長からは、教員との懇談会開催報告、応化会のDX推進、会員名簿・連絡ルートの整備を進めていること、応化会給付奨学金の仕組み作りを進めていることが報告されました。
学生委員会からは、岡副委員長より、新入生歓迎会、オリエンテーション、オープンキャンパス、若手OBとの縦割り交流会をオンラインで開催したことが報告されました。また、輿石委員より、応化委員女子会が発足し、横縦のつながりを広げるため精力的に活動していることが紹介されました。
若手部会からは、尾崎部会長より、Chem-is-Try!のスローガンの元、次代を担う世代代表として次世代応化会ビジョンの策定や情報基盤の構築を精力的に進めていることを報告されました。特に若手OB視点で、応化会企画のポートフォリオ分析から、今後、自分のためになるキャリアチャレンジや異業種交流会等の企画を充実させていきたい旨の提案がありました。
友野中部支部長からは、交流講演会、中部支部若手部会の立ち上げ状況が報告されました。本部の若手とも連携して活性化されていくことが期待されます。澤村関西支部事務局長からは、役員の若返りを図り(齋藤支部長(新33回)、澤村事務局長(新53回)、三品事務局(新59回))、支部・本部連携して、これまで魅力あっても参加できなかった世代に向けてオンライン等を活用して活性化していきたいという意気込みが話されました。
世の中が急速にデジタル化に向かっていく中、応化会活動においてもデジタル技術の活用が欠かせません。若い人の頭で将来の情報基盤の構築検討が進められています。若手部会の劉氏(新56回)から、コミュニケーション・プラットフォームを用いた構想の進捗状況が報告されました。事務局機能の負荷低減や会員の皆さんがアクセスしやすい環境になっていくことが期待されます。
100周年担当の下村副会長より、2023年には応化会100周年を迎え、多くの応化会会員の力を結集する機会としたいことを強く宣言されました。記念講演会・記念式典、会報の100周年特集号の準備が進められています。応化会給付奨学金については、次世代展開として、博士人材の発掘と支援強化を行っていく方向性が示され、10月より募金が開始されました。ぜひご協力をお願いいたします。(詳しくは応化会ホームページよりご覧ください)
各世代のアクティビティ紹介
評議員の各世代代表者4名から、それぞれの世代の交流活動状況が報告されました。
 左より:新20回朝山氏、新36回古川氏、新42回市場氏、新59回古田氏
左より:新20回朝山氏、新36回古川氏、新42回市場氏、新59回古田氏
新20回朝山氏からは、名簿整備を進め、研究室ごとの代表者を置き9割の方のメールアドレス・住所を確認できたこと、新36回古川氏からは、2017年の同窓会時から名簿の整備を進めて、オンライン同窓会や野球観戦、ゴルフなどの交流を進めていること、新42回市場氏からは、後輩たちとFacebook等でゆるくつながっていて、その経験から、小規模のオンライン飲み会をミドルシニア層にお勧めしたいとの提案がありました。新59回古田氏からは、応化出身者が多数いる稲門弁理士クラブの活動について報告がありました。現在の日本弁理士会の会長は応化出身の新34回の杉村純子氏なのですね。
応化会活動に対する意見交換
これまでの応化会活動報告や各世代のアクティビティのご紹介を受けて、応化会活性化のためのご意見・ご提案をいただきました。いただいたご意見と各委員会等での課題を合わせて、より一層存在感のある応化会に向けて改革を進めてまいります。ぜひ忌憚のないご意見を引き続きお寄せください。
濱会長による総括
最後に濱会長より今回の評議員会の総括として、次世代に向けた応化会活動を応化会100周年の柱にしていきたいという決意が述べられました。
今回はまだ懇親会を開催できる状況にはありませんでしたが、次回はぜひ懇親会ができることを期待して、旧交を温めつつ、新しいWASEDA応化会を形作っていきましょう。評議員の皆さまには、各世代の連絡先整備を進めていただき、1年半後の応化会100周年にはぜひ多数の方にお集まりいただきたいと思います。
(文責:基盤委員会 梅澤 宏明、写真:広報委員会 学生委員会)


●長澤 寛一(昭和25年卒・燃 6 回)
今のところ無事消光いたしております。
●樋渡 幸訓(昭和28年卒・新 3 回)
91才になりました。コロナで人混みに行かれませんので自宅から余り遠くない相模川の畔を散策などしております。
●堀内 弘雄(昭和36年卒・新11回)
卒業60年になっても学生時代を思い出します。理工展で泊まり込んで準備を…友人の寝袋姿が写真にあって笑ってしまいます。早慶戦の後の新宿も…今はコロナでダメなのでしょうが…。若い方々の御活躍と応化の発展を祈っています。
●飯田 康夫(昭和46年卒・新21回)
人類史への化学寄与が再着目される中、若々しい研究を頼もしく拝見。願わくば、“勿体ない” “お互い様” 等の日本価値観を具現化する発明・発見で社会貢献し、世界で尊敬されるように。概念寄与なければ無視されます。日本は。“排ガスなし”の新幹線が、中国のものと米大統領が引用したように。実体も印象までも。
●貝沼 雅人(昭和59年卒・新34回)
5 月より37年間勤務したシチズン時計を退職し、日本時計協会に努めております。
●横田 昌明(昭和54年修・大27回)
いま、私たちにとって大切なのは、如何に困難な状況のなかでも平然としてベストをつくし、学問の流れを止めないことだと思います。同窓の諸兄の皆様の健康と、益々のご活躍と、少しばかりの幸運を心より祈念しております。


 8月7日(土)に第2回若手会員定期交流会をオンライン会議ツールZoomにて開催さされました。この会は第1回(5月15日開催)に引き続き主にB1~B3までの学生と若手OB・OGの交流を深める目的で行われました。初めに早稲田応用化学会の副会長も務められている平沢先生よりご挨拶をいただき、その後OBのお三方のご講演、テーマごとに分かれての懇談会という順で実施されました。
8月7日(土)に第2回若手会員定期交流会をオンライン会議ツールZoomにて開催さされました。この会は第1回(5月15日開催)に引き続き主にB1~B3までの学生と若手OB・OGの交流を深める目的で行われました。初めに早稲田応用化学会の副会長も務められている平沢先生よりご挨拶をいただき、その後OBのお三方のご講演、テーマごとに分かれての懇談会という順で実施されました。
学生委員会のHPに報告が掲載されました。 ⇒ こちら
学生委員会

これまで、“バスツアー”で関東近郊の企業の工場を見学する企画で運営してきましたが、コロナ禍の環境で、大学サイド/企業サイドいずれも団体での行動が制限されており、今回は新たな試みとして、大学と企業をリモートで結んだ “企業訪問” を行いました。
以下文中では リモートにおける行動、役割であることを明確にする場合に“ ” を付しています。
リモートの利点を活用し参加者は約50名、また、OB、OG懇談会ではDNP各サイトからの参加がありました。
1.概要
【日程】 2021年6月10日(木) 16時40分~18時40分
【”訪問”先】大日本印刷株式会社:DNP
1) パート1;P&Iラボテクノロジー
P&I:Printing Technology & Information Technology
参加学生の個々のデバイス(ノートPC、スマホなど)とDNP五反田をリモート接続ツール:Teamsで接続
2) パート2:OB、OG懇談会
【参加学生】対象:学部1年生、2年生の希望者
(3,4年生、修士学生からも希望者の参加がありました)
参加者:約50名
【”引率”】山口潤一郎教授、須賀健雄准教授
【DNP】ファインオプトロニクス事業部 鈴木智之@五反田 新31 1981年 加藤・黒田研
研究開発センター 那須慎太郎@つくば 新52 2002年 黒田研
高機能マテリアル事業部 住田裕代@北九州戸畑 新68 2018年 小柳津・須賀研
2.詳細
1) パート1;P&Iラボテクノロジーの説明(DNP ホームページより)
DNPの技術は、モノづくりの基礎となる「微細加工」「精密塗工」「後加工」と、それを支える「企画・設計」「情報処理」「材料開発」「評価・解析」に大きく分かれ、それぞれの技術が拡がり、高度化することで、さまざまな技術に発展しています。印刷から発展したDNPの技術は、現在も進化を続けています。
しかし、DNPの強みは多くの技術を持っていることだけではありません。これらの複数の技術を掛け合わせ、新しい価値を持つ製品やサービスを生み出せることが特長です。
例えば「本」をつくる際は、基礎となる印刷技術や製本技術を掛け合わせ、さらに素材となる紙を掛け合わせて作られています。その後、素材となる紙をフィルムや金属に置き換え、さらに高度化した技術を掛け合わせることで、パッケージ、建材、エレクトロニクス部材などの製品やサービスを生み出してきました。
◎技術の樹
◎DNPの製品例
◎参加学生の感想(代表的なものをピックアップ)
2) パート2:OB、OG懇談会
参加学生からの下記の質問を中心に、OB、OG懇談会を実施しました。
また、山口先生から下記の質問があり、OB、OGの経験の中から具体的な回答・説明がありました。
◎ 参加学生の印象に残ったこと(代表的なものをピックアップ)
最後に応化会の活動として
の案内を行いました。
以上