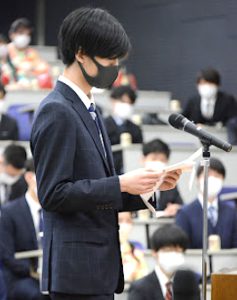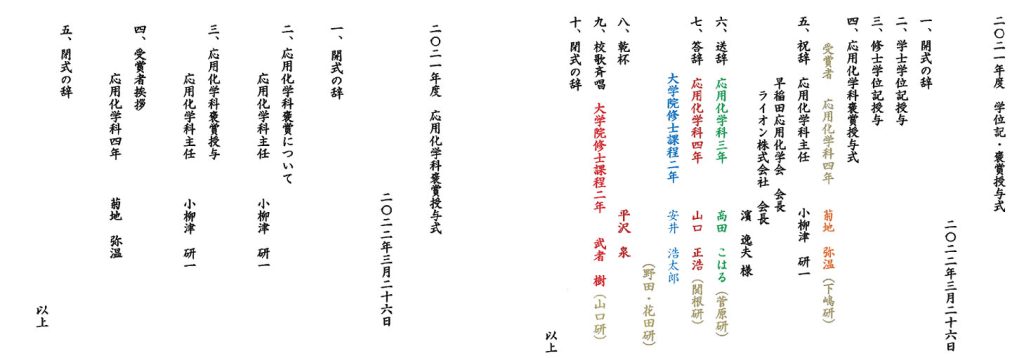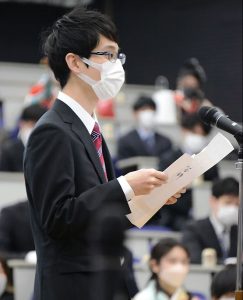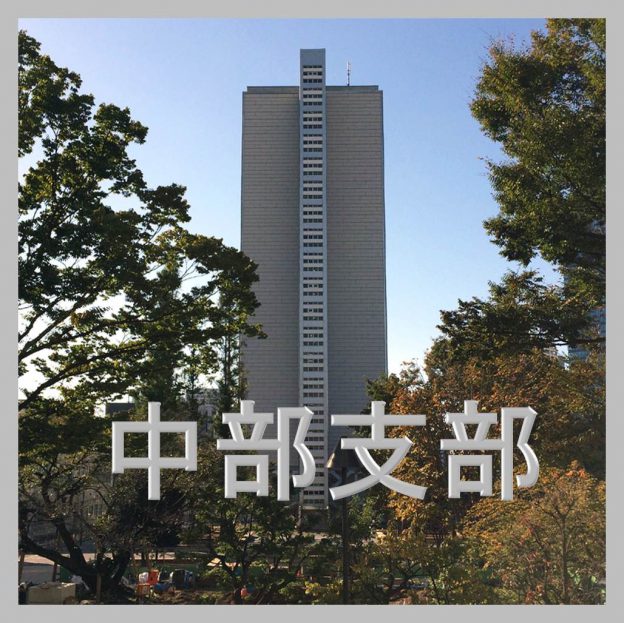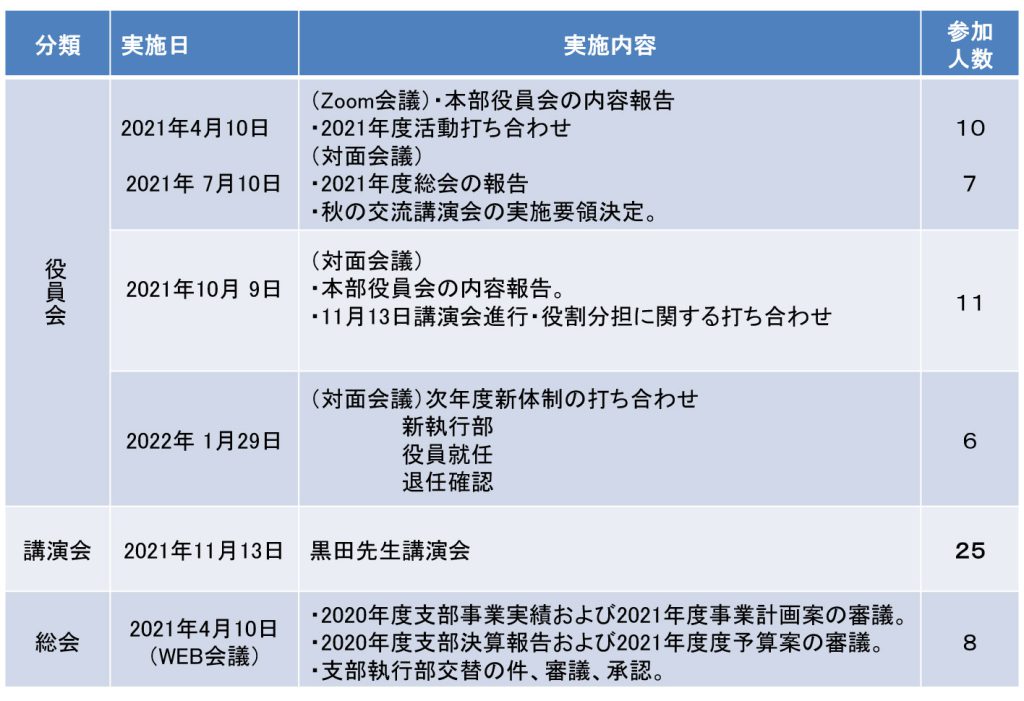三菱ケミカル(株) 山崎正典さん
卒業生へのインタビュー企画
多くの応用化学科卒業生が社会に出られて活躍されています。実社会での経験は業種や職種によっても様々であり、卒業生の体験談は実社会で日々活躍されている卒業生の新たな視点への着眼点になったり、在校生にもこれから進むべき未来において貴重な体験が含まれていると思います。
そこで、各方面で活躍している卒業生に現在の自分の立ち位置について語っていただくとともに、インタビュー形式をとることで現役学生を含めた各世代の応化会会員間のコミュニケーションラインの構築と、社会における経験値をほかの卒業生にも共有していただくことを目的とした企画になります。

山崎正典さんには、会社の統合による研究環境の変化や内閣総理大臣賞も設定されている「ものづくり大賞」にもノミネートされた日本古来からの技術に太陽熱を冷房に使う試みを融合させた研究テーマの概要や着眼点について伺いました。
山崎正典さん 《ご略歴》
1992年3月 応用化学科 高分子(西出)研究室(修了) 1992年4月 三菱油化(当時)入社 入社後、三菱化成との合併、三菱化学に、その後三菱樹脂、三菱レーヨンとの統合などを経て三菱ケミカルと会社組織が変動していく中で、新素材研究所、材料加工研究所、ポーラスマテリアル研究所、機能材料研究所、無機材料研究所、Science & Innovation Center Inorganic Materials Laboratoryを歴任され、その間東京農工大にて学位(工学博士・2013)取得
Q. まずは日本ものづくり大賞について教えてください。
A. 「ものづくり大賞」は経済産業省が中心になって2005年から実施されています。日本を支えてきた古き良き文化を継承するとともに、それを新たな事業環境へも発展させて付加価値を提供する人やグループを表彰する制度です。幸運にも、「太陽の熱で冷房する革新的な水蒸気吸着材」で第3回ものづくり大賞の優秀賞をグループとして受賞することが出来ました。

(写真)大学研究室時代 追分セミナーハウスにて
Q. 会社の統合を経験されていますね。統合の際に何か変化を感じたことはありますか
A. 大学では西出研で高分子を学びました。日々多くの実験をこなし、それなりに勉強した自負はありましたので三菱油化(現三菱ケミカル)に入社した時、どんな研究をすることになるのか本当にわくわくしたのを覚えています。
その後、会社の合併・統合のたびに自分が取り組むテーマは変わりました。入社時の複合材料開発、合併後に蓄熱・吸着材開発、統合後には熱マネージメント材料や酸化物ナノ粒子など。今考えると、合併、統合する相手の得意な分野をテーマに取り入れ、シナジーを出そうとしていたのではないかと思います。例えば、「ものづくり大賞」の吸着材は旧三菱化成のゼオライト合成技術がベースとなっています。
合併や統合の際には、人的な面でも大きな変化があったと思います。それぞれの会社で持つ専門・技術の広がりが人を介して融合し、新たな材料を共同で開発するといった取り組みが増えたように感じています。単一の技術で解決できる課題は少ないので、製品化を進めていくための最適な土壌が出来ていったと思います。
「太陽の熱で冷房する革新的な水蒸気吸着材」はもともとが有機化合物を使った相反応の応用研究を進めていたのですが会社が保有していたゼオライト合成技術が生かせることに気がついて方向転換しました。会社に研究成果が蓄積されていることで違う視点での研究成果が得られることが強みに繋がっていると思います。
Q. ものづくり大賞にノミネートされた「打ち水」の技術について教えて下さい
A. 霧状の水滴を上からまいたりする設備がありますが、これらは特別な材料や装置を必要としないエコな冷房とみることができます。水の潜熱は凡そ2454(kJ/kg)@20℃程度で比熱が4.2(kJ/kg・℃)ですので、10gの水が蒸発するだけで水1kgを約6℃も低下させることができることになります。ゼオライトという多孔材料を使って、強制的に水を吸着(蒸発潜熱の利用)させ、太陽の熱を使って脱着(自然エネルギの利用)させるというサイクルを回すことで、「打ち水」の現象を実用的な冷房に使えるということになります。
Q. 研究テーマも何度も変わっていらっしゃるようですが、常に新しいものを創製していかなければいけないプレッシャーなどありますか
A. 正直、プレッシャーはありますが、社内では新規のテーマ提案をいつでも行えます。それを支えるために10%カルチャーという制度があり、主担当の業務以外に研究者個人が興味を持ったことに取り組む時間と幾ばくかの予算が与えられています。その様な制度をうまく利用して、最近では積極的に若手が発信をしています。また、若手研究者とのコミュニケーションは大切にしています。様々な年齢層の人たちが、現状をどのように考え、どのようなことが課題と思っているかを聞くことは、働きいやすい職場や活気のある職場の実現には必須と考えているからです。研究を一人ですることはできないので、普段から多くの部署の方々とコミュニケーションを持ち、協奏を進めたいと思っています。
専門性を究めていくことと多岐に渡る可能性を一つのテーマに拘ることなく展開していくことのどちらが好ましいかは難しいテーマだと思います。ただ、技術やナレッジの繋がりを強化しておくことは一つでも上手くいく研究成果があるとテーマ全体として生き残っていくことも出来ますし、広い視野を持つことは意識するようにしています。
Q. 後輩に対して伝えたいことを教えて下さい。
A. 「大学の研究内容について簡単にご説明ください」、と言われると最近の学生さんは研究内容をびっくりするほど上手に説明します。一方、どこを自分で考え、工夫したのかを問われると、答えに窮することが多いようです。研究がうまくいくことは重要ですが、それよりも「なぜ、そのような検討を行ったのか」を振り返ってみることが大切と考えています。そこには確かに自分の考えがあると思います。自分で仮説を立て検証を繰り返す中で、研究を進める主体があくまで自分であることを認識し、有意義な研究室生活を送っていただければと思います。
また、研究に限らず多くの人とつながりを持つことも大切と思います。多様な個性を認め、相互理解を深めることから新たな発想が生まれ、テーマ提案につながることもあるからです。大学時代は、先生やドクターの方からテーマを与えられ、その範囲で研究を進めることがほとんどです。しかし、会社では、何をやるべきなのか、どのようなアプローチでそれを達成するのか、どんな強みや弱みがあり、弱みをどこの誰と一緒に解決できるのかなどを将来状況も考慮しながら、自分で提案していくことが求められます。その時、人のつながりがきっと皆さんの力になってくれると思います。
学生時代は研究室で与えられたテーマをこなすだけで精一杯で、それ以外の分野に興味を持つ余裕はなかなかありませんでした。しかし、入社以降、特別な場合を除いて、1つの製品は多くの技術の塊で出来ているということを実感しました。自分の専門にとらわれず、専門以外の分野に興味を持つことも大切と思います。

インタビュー後記:
会社が強みとして持っている研究領域についても、10年後20年後を見据えた時に時代遅れの技術になっている可能性もある中で、社内の風通しをよく、異分野の研究テーマについても情報共有することは、新しい提案が次の研究テーマとして採択されるかどうかは別にしても研究者としてのモチベーションに繋がっているという話は興味深く、特にオンラインが導入されたことによりその強みを活かして普段は対面で接することが出来ない事業所の方々とも情報共有することが出来るという話は新たなイノベーションに必要と感じました。
また、若手に対しては自分が想定していた研究テーマとは違う領域での研究においても自分が何のために研究しているのかという自分自身の軸を持っておくことで将来のチャレンジに繋がることもあるので頑張ってほしいとの強いエールを頂きました。
(聞き手) B3.吉田七海、B3.小林菜々香、新68.住田裕代(広報委員)、新39.加来恭彦(広報副委員長)