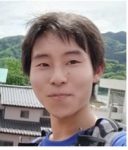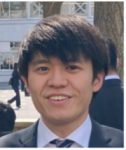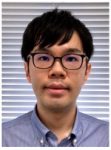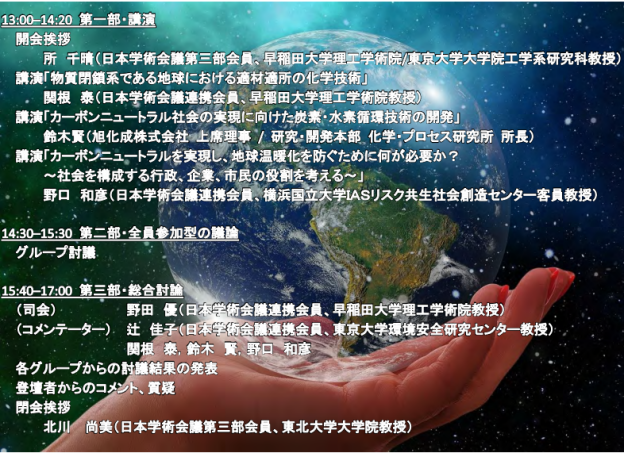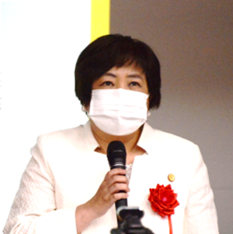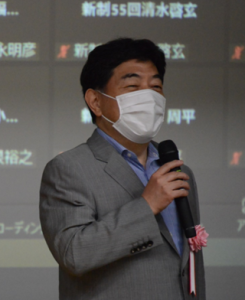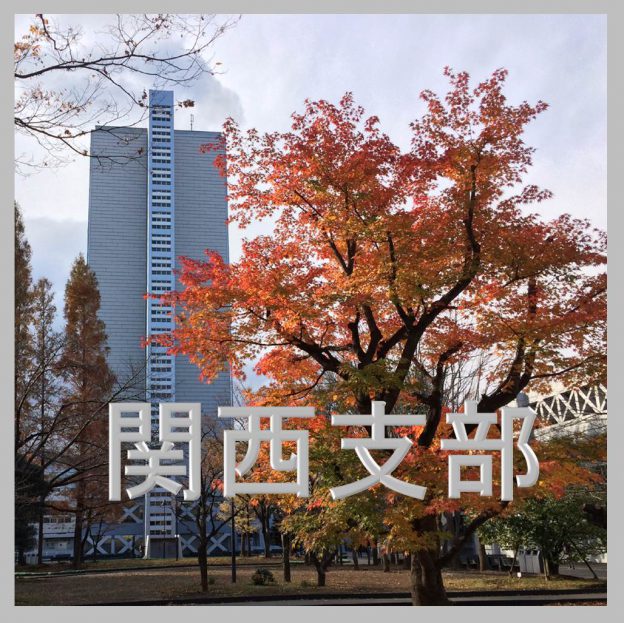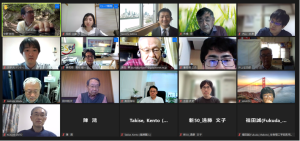2022年8月27日:15:00-17:00
西早稲田キャンパス、61号館102B教室
講師:市場有子さん、福所しのぶさん
【目的】自分らしいキャリアを踏み出すきっかけを作ること
【ゴール】今必要とされるキャリアの考え方を知ること、自分の持つ価値観や強みを知ること
【概要】
人生100年時代、VUCAと言われる不確定な現代、長らく続いた年功序列や終身雇用といった日本型雇用は終焉を迎えようとしています。いつ何が起きてもおかしくない世の中では、所属する組織は成長の舞台であると考え、自分自身のキャリアを蓄積ことが何よりも重要とされています。一方で、理系の専門知識を持つ若手研究員は、その専門性の高さが強みとなりますが、社会人となって数年たつと、長期的キャリア形成やプライベートと仕事のバランスに戸惑う場面も見られます。今回のセミナーでは、理系×キャリアコンサルタントの我々から、社会に出る前に知っておいた方が良いキャリアの知識をお伝えし、ワークを通して自分らしいキャリアを踏み出すきっかけをご提供できればと思います。
1.ミニセミナー「人生100年時代のキャリア形成について」
日本人の8割がキャリアの迷子になっているという現状があり、迷うことは普通だが、どういうキャリアが求められているのか、どう考えるのかを知っていくことは重要。
現状の説明
VUCA(= Volatility(変動性),Uncertainty(不確実性),Complexity(複雑性),Ambiguity(曖昧性))の時代、人生100年時代、長期のキャリア形成:
経団連に所属する企業トップからも終身雇用の終焉を示唆する時代に来ている。これまではキャリアは一つの組織で昇進するための過程だったが、現在は能力を蓄積していく過程で組織は経験を与えてくれる場になっている。組織、昇進権力、地位給料(伝統的キャリア)から個人、自由・成長、心理的成功(自律的キャリア)に代わってきているが、自律した従業員の増加を80%以上の企業が望んでいる(優秀な人材の定着や生産性向上を上回っている)。
続いて、キャリア自律度診断(15項目)を用いた説明(自律的人材の診断)を用いて、キャリアアップについてのアクションについて説明があった。
心理的成功:何を伸ばせばいいのか=アイデンティテイ(自分らしさ)×アダプタビリティ(社会への適用)
これを伸ばすために3つの社会関係資本が重要(①ビジネス資本=スキル、資格・語学、経験,②社会関係資本=コミュニティ、プロボノ・副業、スクール・セミナー,③経済資本)
実際に自立度を伸ばすために、今の自分を知り、目標設定をしたときの現状からのGAPを認識し行動計画を立てて(1-3年)、実行(3-5年)実施しキャリア蓄積していく:大事なポイントとして、今の状態と目標の両方が明確であること、そのために自己分析が重要になってくる。
2.様々なキャリアパスを知る
研究職のキャリアパス:
目標設定のために、ロールモデル(ああいう風になりたい)を。そのために人付き合いが重要。
経験上、周りの支援を活用すること:育児と仕事の両立
ライフラインチャートで一定してプラスに振れている人は少ない=悩みはあるのが当たり前=長期的視点で見る
理系の活躍場面:
研究所内では、基礎研究、開発研究、生産研究といったカテゴリーがあるので、自分の興味に応じて選ぶと良い。
研究所外にも理系が活躍できる場面は沢山ある。例えば、
法務、事業部・経営企画
品質保証、知的財産
お客様センター、広報など。
活躍場面は多岐にわたるので選択肢を広く考えておくのがよい。
目標を決める上でロールモデルを定めることがオススメだが、1人に決めることは難しい。家族との過ごし方、余暇の過ごし方、コミュニティとの付き合い方、など多様な人との会話の中からロールパーツを集め、自分なりのロールモデルを形成することが良い。
研究職以外のキャリアパス
出産・育児における負荷は研究職、非研究職ともに同じで研究職以外の例として弁理士の事例について説明があった。博士課程に在学していた2000年頃は、博士号取得者のほとんどがアカデミック研究者を目指すという状況であった。しかし、博士課程なかばで、クリエイティブさへの疑念、ポスドク1万人計画、将来的な家庭との両立など、進路についての悩みが生じた。そんな時期に米国大学内のベンチャー企業でのインターンに参加し、知的財産の重要性を認識したことが転機となった。弁理士や知的財産関係の仕事は、自ら研究を行うことはないものの、身に着けた科学知識を生かしつつ、最先端技術へのサポートができるという点が魅力であると感じている。
転機の乗り越え方についてのヒントについて:
転機は大なり小なり誰にでも必ずくる。大切なのは転機を避けることではなく、乗り越え方を学んでおくこと。
個人のキャリアの8割は予想しない偶発的な出来事によるとのキャリア理論もある。この偶然の出来事をチャンスに変える5つの行動指針として、好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心の重要性について提唱されている。
上記の中でも特に好奇心に関しては日頃からの取り組みが大切と感じており、好奇心から取り組んだことはそれだけで人生を豊かにしてくれるし、一見仕事に関係ないように見えていたことも長期スパンで形になってくることもある。
グループディスカッション
1.個人ワーク
テーマは、「社会人基礎力から考えるあなたのキャリアビジョン」
社会人基礎力は、経済産業省が定義する「職場や実社会で多様な人々と仕事していくために必要な基礎力で、
前に踏み出す力(action) 主体性、働きかけ力、実行力
考え抜く力(Thinking):課題発見力、計画力、想像力
チームで働く力(Teamwork):発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロール力
の3分野12要素で構成されている。ワークではこれらの3分野12要素を題材に、働くうえで最も重要と考えるもの、現時点で最も得意と感じているもの、今後伸ばしていきたいものをピックアップしその理由についても書き出したうえでグループディスカッションを実施した。
2.グループディスカッション
グループディスカッションを通じて、メンバーの能力要素に気がついたものを共有し気づきにつなげる。
3.全体シェア
主体性が得意な人たちだけでも社会は回るのだろうかを考慮しバランスも含めてチームワークへの反映が重要と感じた、アクションとチームワークを得意とするメンバーで構成されていたが、アクションを起こした後共同性を持たないと話が進まない、アクションを重要視しているメンバーが多かったなどの意見が出された。
技術力や知識の深さだけでなくコミュニケーション力・人間力も重要(特にチームワークについては6要素もあるので)
重要と思うもの=価値観
特異なもの=強み・アピールポイント
伸ばしていきたい=伸びしろ・意欲
これを知ることがキャリアビジョンの明確化につながり、自律的キャリアの第一歩になる。
グループワークは、自分の考え方を明らかにして考えを深め、他人の見方も知り、フィードバックによる気づきを客観的に理解できるメリットがある。自己理解や他社との対話の中でキャリアビジョンが深化する。
Q&A:
転機の探し方について:偶然の要素が多いが、「このままでいいのか、自分はどうありたいのか?」という問いやビジョンを持っているかどうかが、偶然をチャンスとしてキャッチできる気づきに繋がっているように思います。意識したものを探しに行くという意識があると気づきもしやすい。
終身雇用についての考え方について:転職についてはネガティブな考え方が多かったがこの数年社会変化が大きい。これに気付いている人と気づいていない人の差が大きい。気づきと状況変化をチャンスと捉えることは重要。そこから自分をどう成長させるかを考えること。
成長の考え方について:これが自分の成長につながったポイント、会社が求めることに近づけたかは一つの指標、目標設定に対する意識を明確に理解してそこに近づけているかを考える:生産だと効率性、イノベーションだと経営学やマーケティング、オープンイノベーションなどが指標になったりする。業務のバリエーションがない場合に効率性を意識するなど。目に見えやすい指標にすることも重要
報告:学生委員会 (岡 順也)、 広報委員会 (加来 恭彦)