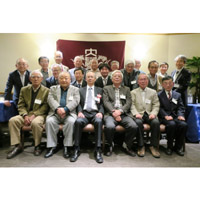2017年4月15日(土)「北京料理百楽名古屋店」にて、第10回中部支部総会と交流会を開催しました。東京大学総合研究博物館特招研究員吉田邦夫氏をお招きし、関西支部よりは市橋宏副支部長と田中航次事務局長に参加して頂いた。
第10回支部総会
三島支部長の開会挨拶に引き続き、 堤幹事より、2016年度の活動および経費実績並びに2017年度活動計画案が上程され出席者全員の賛同が得られました。→第10回中部支部総会上程資料(HP掲載用)
吉田邦夫氏による講演「縄文人の食卓~同位体食生分析~」
吉田氏は放射性炭素(C-14)が規則正しく壊れる現象を時計として使うことによって、人間と自然の営みに関する時間情報について研究してこられ、考古学、環境学、美術史など幅広い分野で研究活動を行っておられます。今回の講演では、人骨と土器に残された炭素・窒素同位体情報をもとにして、縄文人の食卓を再現されました。
①あなたは、あなたが食べたもの(同位体食性分析)
地球にある炭素、窒素には、わずかに重さが違う 兄弟原子「同位体」が存在し、その 比率(安定同位 体比)は炭素については12C(98.90%)、13C (1.10%)、素については14N(99.63%)、15N (0.37%)である。これら炭素や窒素の同位体は 質量が異なるため、植物に取り込まれてセルロースや デンプンに変化したり、タンパク質に合成される際に、 反応速度の違いから安定同位体比からずれることが わかっている。これを同位体分別効果といい、食材の グループによって同位体の割合がわずかに違う。 この違いを利用して、人が食べていた食材を推定するのが、同位体食性分析である。例えば人の髪の毛の炭素・窒素同位体比を分析すると、ベジタリアンの人かどうかを調べることができる。(ベジタリアンの場合、重い13C、重い15Nの同位体比は共に低く、一般的な人と比較して特異なデータが得られる。)安定同位体比の測定は、分析試料を燃やして出来る気体、二酸化炭素と窒素ガスを質量分析計で測定する元素分析計-質量分析計システムによって行う。
比率(安定同位 体比)は炭素については12C(98.90%)、13C (1.10%)、素については14N(99.63%)、15N (0.37%)である。これら炭素や窒素の同位体は 質量が異なるため、植物に取り込まれてセルロースや デンプンに変化したり、タンパク質に合成される際に、 反応速度の違いから安定同位体比からずれることが わかっている。これを同位体分別効果といい、食材の グループによって同位体の割合がわずかに違う。 この違いを利用して、人が食べていた食材を推定するのが、同位体食性分析である。例えば人の髪の毛の炭素・窒素同位体比を分析すると、ベジタリアンの人かどうかを調べることができる。(ベジタリアンの場合、重い13C、重い15Nの同位体比は共に低く、一般的な人と比較して特異なデータが得られる。)安定同位体比の測定は、分析試料を燃やして出来る気体、二酸化炭素と窒素ガスを質量分析計で測定する元素分析計-質量分析計システムによって行う。
②縄文人の食卓への二つのアプローチと日本列島の食料資源
縄文人の食卓を推定するため、「人骨のコラーゲンの分析」(長期間の情報、年齢、男女差などの個体の情報)と「土器付着物の分析」(短期間の情報、一回または複数回の調理の情報)」の二つのアプローチを行い、過去の日本列島の食料資源の炭素・窒素同位体比の情報(C3植物、C4植物、草食動物、海産貝類、海産魚類、海産哺乳類)から、縄文人の食卓を推定した。
③縄文人骨に残された痕跡
縄文人骨から硬タンパク質(コラーゲン)を取り出し、同位体比を分析すると、居住地域による特徴が見られる。北海道では、およそ6000年の間、海獣に依存した食生活が続いていた。内陸部では、草食動物に依存していた。貝塚人は、海産物の依存が多いものの、貝類のみを食していたわけではなく、草食動物を多く食していたことがわった。また、人骨分析を行った集団の中で、集団から離れた個体の存在が見つかった。異なる食文化をもつ個体(シャーマンなど)? あるいは、食文化が異なる集団から移り住んだ個体?があったと推定される。
④土器に残された痕跡
火炎土器は祭祀のため、神に献げるものの煮炊きに使用されていたと推定される。火炎土器に付着した炭化物(調理した食材のおこげ)の炭素同位体比とC/N比の分布を測定することで、食材の種類を特定することができる。火炎土器付着物から次のことがわかった。堅果類(どんぐり、トチの実など)を単独で煮炊きした例はない。遺跡ごとにややまとまりが見られる(祭祀のために決められた特別なメニューはなかった)。(信濃川)上流部では、主としてC3植物と陸上動物が調理されていた。(信濃川)下流部と(佐渡)島では、海洋魚、サケ・マスを含む食材が調理されていた。
最後に新たな展開として、脂質分析(分子レベル炭素同位体比分析)の紹介があった。
懇談会
後藤顧問の挨拶と乾杯の音頭で懇談会に入った。両関西支部来賓および大高理事、新村理事および初めて参加頂いた浜名氏にスピーチを頂いた。テーブル毎や吉田氏を囲んだ懇談が盛んで、2時間があっという間に過ぎてしまいました。全員写真を撮った後、フィナーレは堤幹事の「1本締め」で、母校及び早化会の発展と各位のご活躍を期し散会しました。
参加者(敬称略)
(講 師)吉田邦夫(新21回) (関西支部会員)市橋宏(新17回)、田中航次(新17回)、
(中部支部会員)澤田祥充(旧31回)、近藤昌浩(新9回)、三島邦彦(新17回)、堤正之(新17回)、白川浩(新18回)、後藤栄三(新19回)、小林俊夫(新19回)、柿野滋(新 19回)、秋山健(新19回)、谷口至(新22回)、須藤雅夫(新22回)、木内一壽(新24 回)、山崎隆史(新25回)、浜名良三(新29回)、服部雅幸(新32回)、新村多加也(新 39回)、大高康裕(新41回)。
(文責:大高、堤)