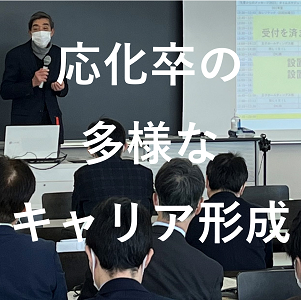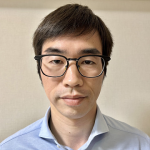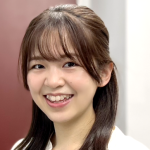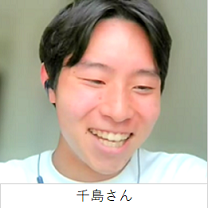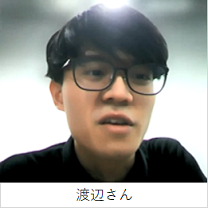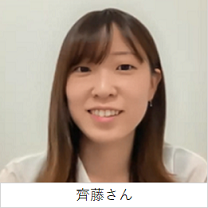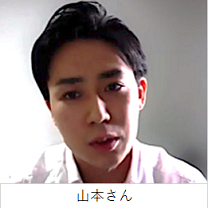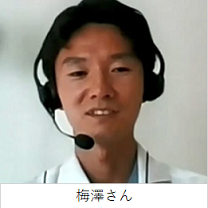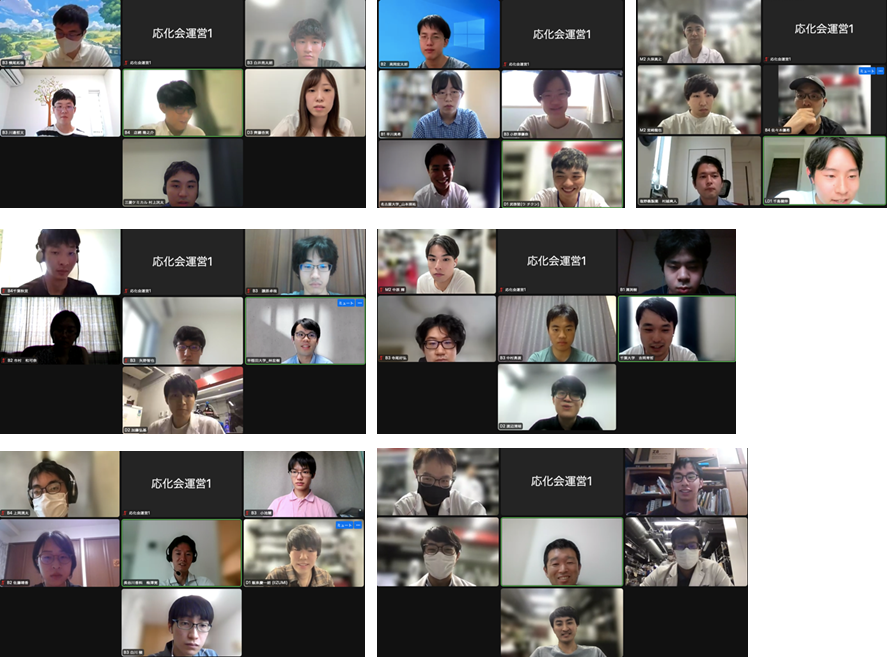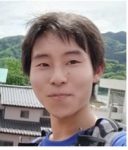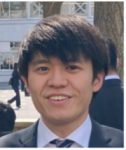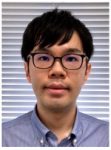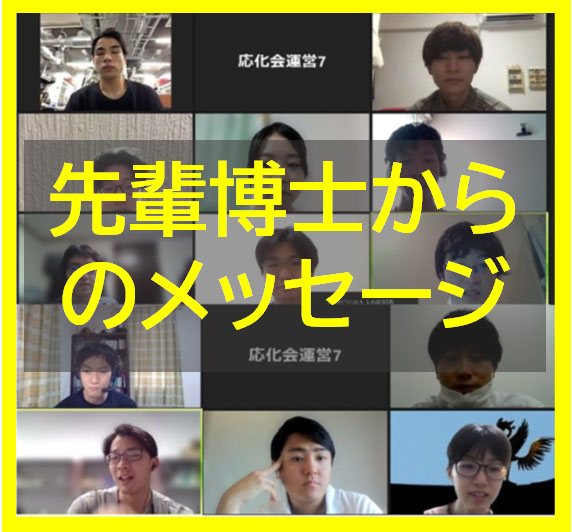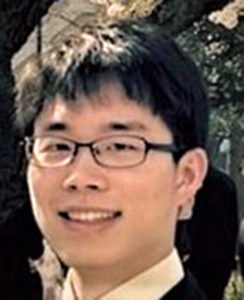【開催日時】 2021年12月18日(土) 13:00-16:00
【参加者】:39名(B2:1名、B3:6名、B4:9名、M1:19名、M2:4名)
Zoomにて開催
第1回の「先輩博士からのメッセージ」が現役の博士課程に在籍している先輩博士から修士課程や学部学生に対するメッセージとして企画されたのに対し、第2回に当たる今回の「先輩博士からのメッセージ」は社会人ドクターからの講演を中心にグループディスカッションを交えて実施された。
開会の挨拶:下村 啓 副会長

下村 啓 副会長
皆さん、こんにちは。
早稲田応用化学会で100周年事業担当をしております新制34回の下村でございます。早稲田応用化学会では博士人材を育成・支援していくことをこの100周年を機に進めることとしております。
博士人材を増していくことによって、より良い世界をつくることにつながると思っているからです。まず、そのためには多くの人達に博士課程をより身近なものとしてとらえて頂くことが必要だと考え、このような企画を行うことに致しました。この開催にあたっては交流委員会の皆さん、教室の先生方、学生の皆さん、そして多くのOB/OGのご努力とご協力とがありました。本当にありがとうございます。この企画はまだ始まったばかりです、これからより良い企画にしていきたいと思いますので、是非ご協力をお願いします。
さて、博士人材支援の面では応化会給付奨学金の取り組みもございます。奨学金については後ほど説明がありますが、その応化会給付奨学金の資金拡充のための募金を始めています。OB/OGの皆さんはよろしくお願いいたします。
本日の会は皆さまにとって意義ある会となることを願っております。それでは今日は皆さま、よろしくお願いいたします。
講演会
講演者①;加藤 遼さん(中央大学助教、2017 西出・小柳津・須賀研究室 博士修了)
演題;『博士号を“取るまで”と“取ってから”』

加藤 遼さん
|
加藤遼さんは高分子化学研究室に所属され、修士課程修了後に新設された先進理工専攻一環博士課程(リーディングプログラム)に編入学され一貫性博士課程を修了されたのちにシカゴ大学博士研究員を経て中央大学の助教として活躍されている。
|
博士課程への進学を決めた理由としては自身の生活環境において周囲に教育者がいたことから大学入学当初より研究者かつ教育者でもある大学教員へのあこがれがあり、学部学生の時点で博士課程への進学を既に決断し、また進学にあたっては同期2名が博士課程への進学を決めたことによる安心感もあったとのこと。
一貫性博士課程へ進学した後には必修単位の多さに研究活動も加わり多忙ではあったものの専門分野と異なる座学や異分野の学生との対話によるナレッジ構築が自身の研究のヒントになることもあったとのことで、さらには海外インターンシップと海外研究機関実習の経験もその後の進路に与えた影響は大きかったそうです。インターンシップで訪れたアメリカ・オハイオ州のアクロンにある日本企業の米国中央研究所では全従業員のおよそ9割が学位取得者で海外での生活が大きな自信につながったとのこと。
一方、博士課程の研究では修士課程から研究テーマを大きく変更し、当初は手探り状態で成果がなかなか上がらない時期もあったが、試行錯誤を重ねてメディアにも取り上げられてもらえるような水素貯蔵プラスチックの作製に成功した。このことから、博士課程においては自由に挑戦と失敗が出来る貴重な時間であったと思っており、自分の行動次第でいくらでも能力を磨き、自分自身のやりたい研究が出来ることを学ぶ貴重な機会になったとのこと。
学位取得後のキャリアとしては、入学当初からの目標でもあった研究者かつ教育者の道を進むことを決断し、またインターンシップなどでの経験から海外で長期の研究に携わりたいとの思いから博士研究員の道に進むことを決断した。在籍したシカゴ大学の研究室では学位取得者は一人で研究が進められる人材とみられることとも合わせ、最も研究に集中できる時間を得ることが出来たとのこと。
以上を踏まえて、修士課程及び学部学生には何となく周囲と同じような進路選択をする漠然とした意識ではなく、自分自身での進路選択を考えて頂ければとのメッセージを頂いた。
<質疑応答>
海外生活におけるメンタルについて:一般学生でも対等に議論する雰囲気があった。ディスカッションについては真っ向から否定されるような場面もあったが基本的には真面目な議論の中でのやり取りであり普段はとても仲のいい仲間たちでメンタルについて気になるポイントはなかった。
国内では研究班を構成して同じ目的に何人かが携わることも多いが、海外における個人ベースでの研究と違いについて:アメリカでも2,3人でチームを組んで1人当たりでは2~3テーマを持つ。テーマ切り替えの判断は早かった印象がある。全体としての研究のスピード感を認識したのはこのシステムにも理由があったように思う。
講演者②;堀 圭佑さん(住友化学、2020 野田・花田研究室 博士修了)
演題;『企業研究者という選択』

堀 圭佑さん
|
堀 圭佑さんは、早稲田大学では化学工学を専攻され、軽量、高導電性を達成し、自立膜の形成が可能なカーボンナノチューブの構造制御によるリチウム二次電池電極のエネルギー密度を向上させる研究に従事されたのちに学位取得後、国内化学企業へ進まれている。
|
博士課程への進学に関しては研究室配属当初はグローバルな企業研究者として早く活躍したいという希望が強かったものの、研究を進めていくうちに、研究そのものの面白さに加えて国際学会に参加することで学位を有する研究者からのインプットや自身の研究内容を世界に発信できる喜びを体験し、研究の継続を強く望み博士課程への進学を決意したとのこと。
一方で、博士課程進学に関して、金銭面、就職活動、国内企業における博士号の有用性について不安もあった。これら不安材料については実際に博士課程進学後および就職後で考え方が大きく変わった。
|
不安点
|
不安内容
|
実際の状況
|
進学後の印象
|
|
金銭面
|
学費や生活費の工面への不安
|
早稲田の奨学金制度の充実、また大学からのサポート
|
奨学金制度などで学費の免除と助手にも採用されたことで収入も安定した。
|
|
就職活動
|
博士卒の就職内定率や採用企業数
|
化学系企業の多くは博士人材を採用
|
研究を通じた縁もある。
研究発表会で自身の研究内容に興味を持って頂いた。ひたむきに研究に没頭出来たためかもしれない。
|
|
博士号の有用性
|
修士卒との差別化、学位取得者のプレゼンス
|
自身の研究能力を高める、研究そのものの楽しさはモチベーションに影響しない
|
企業に進んでも周囲に学位取得者が多く(3人に1名程度)、具体的な実験計画や実験指示、結果分析及び次のステップでの実験方針決定など自分の裁量で研究内容を決定できる範囲が広く、主体的に考えて挑戦できる環境を頂けた。
|
また、博士課程に進学した利点として、
在学生数が多い応用化学科において個人個人に研究テーマがありディスカッションを通じて様々な分野の知識が身に付くことで、社内外のスタッフとの交流においても内容が理解できずに話についていけないということがないこと、
1つの研究テーマについて熟考することで論理的思考力を身につけることが出来、企業においてスピード感ある研究が求められる場面でも地力をつけていることで効率よく研究していくことが可能になった
のポイントをあげておられた。
以上を踏まえて、どの様な人生を歩みたいのかを考えて、博士課程進学は一つの選択肢としてじっくり考えて自分自身の進む道を選択してほしいとのメッセージを頂いた。
<質疑応答>
自分で実験を組んでいくことで大変だったと思ったことは:思った時にすぐにやりたいという気持ちが強くワクワク感があった。思った時に直ぐに動き始めた時に結果が伴わないことも多々あると思うが結果には必ず理由があることを突き詰める面白さをまた感じた。
講演者③;中村 夏希さん(東芝、門間研究室D3)
演題;『社会人博士に至るまで』

|
中村夏希さんは早稲田大学では物理化学(電気化学)専攻で修士課程で国際論文誌に第一著者としての研究論文を2報公開、小野梓賞受賞後企業に進まれ、研究所移転に伴い東京近郊に職場が配置転換されたのを機に博士後期課程に入学され、現在学位論文を取りまとめられている。現在の研究はイオン選択制の高い高分子フィルムを用いた効率性の高いリチウム-硫黄電池の開発である。
|
中村夏希さんは、修士課程の学生時代に論文投稿を既に行っていたことにより、博士課程にそのまま進んで研究を継続するより企業での新しいキャリア形成を求めて企業に就職という選択をされたが、一方で博士課程での研究推進についても強い興味を持っており論文投稿について学生に分かりやすく説明をされた。
学生時代に論文投稿する意義として、論文化出来るほどの成果ではないと考えたり論文にまとめるのが大変ではないかと躊躇したりする点について、学生時代に授業料を納付して学べる機会が与えられていないのにチャレンジし経験を積まないのはもったいないとのポジティブ思考で、論文誌も種類が多く、研究成果の内容に応じた投稿先を選ぶことや、現時点では評価されないと思われがちな成果であっても将来の糧になる可能性があること、また論文投稿の取りまとめのプロセスにおいて自身の研究成果の発表や公開を通じた成果の開示能力が身に付くといった利点を説明された。
そのためには研究の流れをしっかり見極めて十分な調査に基づき仮説を立て検証実験を実施することが重要で、結果分析とその発表により次の課題の見極めを行いまた十分な調査を実施することで研究を発展させていくことが出来ることを示された。
一方で、日本でのジェンダーギャップレベルは2021年次の調査においても先進国中で下位にある現実もあり、ライフイベントで研究活動の中断が発生する場合で企業内評価で有利に働かないなどの課題は存在することも指摘された。ただ、社会変動の大きな時代でもあり、将来を見越して有力な資格取得を考えるのも必要で博士課程でのスキルアップも考慮する選択肢であることを特に女子学生に向けてエールも送られた。
<質疑応答>
社会人としてのキャリアを継続しながら学位取得を目指す選択肢について質問があり、社会人ドクターに関しても会社から学位取得のために派遣されてくるケースや中村さんの様に自分で希望して博士課程に進学される方もいることを説明された。中村さん自身は入社当初から博士課程を視野に入れていたことから、入社時にキャリアパスを設定する時に会社にも希望を出し、希望が通り社会人ドクターとして進学出来たので早めに動くことも一つの方法だと思うと回答された。
また、女子学生へのメッセージとして研究者を続ける過程でジェンダーギャップを感じたことはないとのこと。研究分野にもよると思うが全体数としてまだまだ研究機関においては女性数が少ない現実はあるがその点はポジティブに捉えているとのこと。
座談会
講演会のあと、講演者3名に加えて博士号を取得している卒業生と現在博士課程に在籍している在校生を交えてブレークアウトルーム6室に参加者を分けて、博士課程や関連する質問事項を取り上げ自由闊達な議論を実施した(20分間のブレークルームセッションを3回実施、参加者がなるべく多くの博士課程経験者から話を聞ける様に配慮した)。
座談会参加者は以下の通り(敬称略)
加藤 遼 西出・小柳津・須賀研究室出身
堀 圭佑 野田・花田研究室出身
大島 一真 関根研究室出身
伊知地 真澄 平沢・小堀研究室出身
徳江 洋 西出・小柳津研究室出身
山本 瑛祐 黒田・下嶋・和田研究室出身
村越 爽人 細川研究室出身
佐藤 陽日 細川研究室出身
梅澤 覚 木野研究室出身
吉岡 育哲 桐村研究室出身
村上 洸太 関根研究室出身
林 宏樹 門間研究室出身
中村 夏希 門間研究室
金子 健太郎 野田・花田研究室
齋藤 杏実 山口研究室
女部田 勇介 本間・福永研究室
林 泰毅 下嶋研究室
渡辺 清瑚 小柳津・須賀研究室
渡邊 太郎 木野・梅野研究室
曹 偉 桐村研究室
中軽米 純 細川研究室
加藤 弘基 山口研究室
松田 卓 関根研究室
疋野 拓也 下嶋研究室
クラーク ヒュー 細川研究室
博士後期課程学生への支援体制:基盤委員会 斎藤ひとみ委員

斎藤ひとみ委員
応用化学会のサポートの目的は、経済的支援に加えて博士課程に進学したネットワークの強化にもある。2010年以降の博士後期課程修了者は約90名に達し、進学者の内訳は内部進学が85%、他大学からの編入が6%、社会人が9%であり、ほとんどが修士課程からそのまま博士後期課程に進学している。学位取得後の進路としては過半数が企業に就職している。早稲田応用化学会では、早期から博士人材との交流機会を増やし、博士後期課程に関する真の情報を共有することで、様々なキャリアパスを示す体制を構築している。
博士課程学生の支援体制としての奨学金制度は学外のプログラムとして貸与型、給付型などあり、学科内の奨学金制度は全て給付型で応用化学会の奨学金制度は充実している。学内では早稲田オープンイノベーションエコシステム挑戦的研究プログラムも新設された。奨学金制度を有意に活用して研究室生活の充実を達成頂きたいと考えている。世界的にも博士人材の需要は高くなっており、日本でも博士人材への需要は増加傾向にあることの説明があった。また、応化会奨学金制度は充実してきているので、対象を学部学生にも広げて博士課程に進学する学生を主に審査、奨学金供与を実施していく。
閉会挨拶:橋本 正明 副会長

橋本正明副会長
本日は大変内容の充実した、また意味のある催しを開催できたと思います。この企画を推進し、ご協力いただいた方々、お話をしてくださった博士の皆様に心からお礼を申し上げます。
いくつかの座談会に加わって、印象に残った質問に、いつのタイミングで博士進学を決めたか、また親にその進学をどのように説得したかというものがありました。
確かに私の世代もそうですが、皆さんのご両親の世代には、世の中に早く出て現場を知ることが第一という考え方がありました。戦後のかなり長い期間、日本を支えてきたエンジニアに対しては、自分の働く現場の知識をはやく身に着けて、その知識をベースとして、その生産性(効率)や品質、安全を日々改善し、国際的な競争力を築くことが使命でした。トヨタはまず顧客のニーズをよく知ること、自分の工場の現場の状況をよく見ることから継続的な日々のカイゼンに取り組み、競争優位を築きました。
しかし今日では状況が全く変わってきています。生産現場の機械化や自動化も進み、またISOをはじめとする管理システムが普及定着してきた結果、一定のフェーズ内における新たな改善は限定的になってきました。改善だけで大きな競争優位を得ることは難しくなっています。
今日の競争優位は、従来の制約であったものを飛び越えていく、言い換えれば従来より更に上位のフェーズにステップアップする新しい発想や技術が必要になっています。そこに博士人材の活躍が期待されています。国際間において学術論文数や被引用論文数が競争力の一つの指標になっているのはこうした背景からです。
博士になるというのは、一つの領域で先端の研究に携わるということです。先端の経験、即ち一つの山の頂上から周囲を見渡す視点を持つという経験は非常に大切で、社会に出て何か仕事上のミッションを与えられた時に、目先の作業課題ではなく、高所から全体を俯瞰するという視点をもって、大きなブレークスルーやジャンプアップの可能性を追求できるからです。
現在はこうした能力が、国や企業の競争力の基盤になっています。
皆さんの将来の活躍の可能性を広げるためにも、博士進学を選択肢の一つとして是非お考えいただきたいと思います。



博士人材交流会
講演や座談会にご参加いただいた博士人材の皆様にお集まりいただき、今後の開催に向けたご意見を収集する目的と、博士課程の皆様や博士号取得後社会で活躍されているOB/OGの皆さまとのコミュニケーションの場として交流会を開催した。今回はSpatial Chatをコミュニケーションツールとして設定し、自由に懇談していただいた。

Spatial Chat
(早稲田応用化学会 基盤委員会、交流委員会、広報委員会)
以上