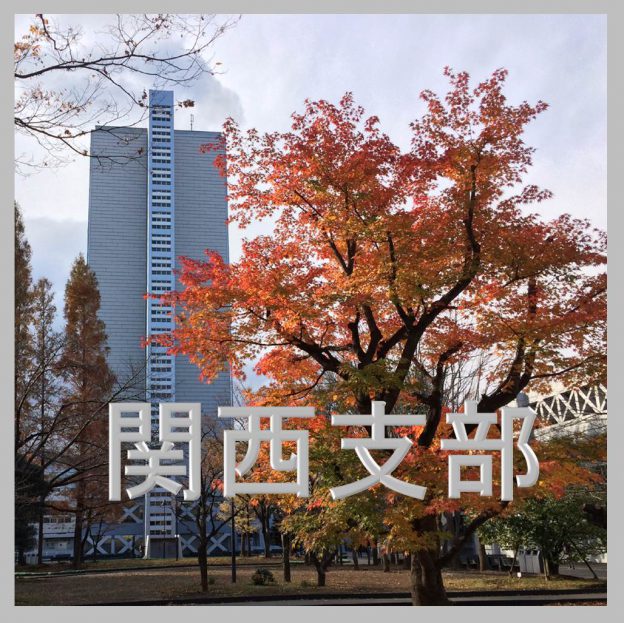2025年度早桜会秋季講演会を2025年9月20日(土)に中央電気倶楽部にて実施いたしました。今回の講師には岡義久様(日本触媒 顧問)をお招きし、「計算機の進歩と私…そして、次の世代へ」という演題でご講演して頂きました。
【講師】岡義久氏 (日本触媒 顧問, 新33回)
【概要】
高校生の時に関数電卓を色々と使っていく中で数学の面白さを感じると共に、計算機のスピードの限界も感じていた。大学時代に一気にPCが進歩していく中で、研究室でも本格的にNECのPCが導入され、関数フィッテイングに勤しんでいた。PC-9801という複雑なプログラムが組めるPCを使用していた。しかし関数フィッティングはあくまで関数フィッティングであり、物事の本質は何か、どういう現象が起こっているのかを理解することが大切だということも大学時代の恩師から厳しく指導して頂いた。
日本触媒に入社するとプラント設計の部署に配属された。当時は電卓と24色の色鉛筆を使ってプラント設計を行うという非常にアナログな方式であった。入社2年目にプラント設計のプログラムを作成した。色鉛筆で2日かかっていた設計が数秒で出来るようになり、これまで1か月かかっていたプラントの性能解析がボタン1つで出来るようになった。一気にデジタル化が進んだ時代だった。1990年代前半にはプロセスシミュレーターが導入された。これは非常に難しい計算が出来るため、様々なことに利用できる非常に便利な物だった。計算速度も上がり、少ない改造投資で増産することが可能となった反面、基礎知識が無くても設計できてしまうことからブラックボックス化が進むという負の側面もあった。
その後2010年までは技術部長を務めていた。そこで過去の知識が消失の危機にあるという事実に直面した。というのも、紙の資料は字が消えかかっている物もあり、現場では都度変更が繰り返される中で資料がそれに追従していっていないケースも多く、情報の質も判別出来なかった。
その後は工場長や教育センター長を歴任。その中で若手の基礎知識の欠如や係長クラスの経験不足など、色々な課題に直面した。教育の仕組みを見直す必要に迫られ、昔は行わなかったような教育も随分やるようになった。女子の受け入れ体制も整えたが肝心の応募が無く、その点は課題である。継続的に教育をし、会社が粘り強く指導を続けることで、従業員は着実に成長しているという事例もあり、大事なことはしつこく言い続けることが大切である。
今後の展望としては、少数精鋭での運転マネジメントということになると考えられる。優秀な少数の人間で重要な部分をこなし、そうでない人は指示されたことを着実にこなす、という役割分担になるであろう。またDXによるサポートも期待される。将来展望としては無人で稼働し、遠隔で監視して、異常時は安全に自動停止という所を目指したい。AIブームの時代であるが最終的には人が判断しなければならない。AIには課題も多く、どこまで信頼性が持てるのかは人間が見定めるしかない。
講演後は質疑応答の時間も設けて頂きました。若手教育や女子雇用など、今日的話題も多かったため、参加者の皆様にて活発な議論が行われました。最後になってしまいましたが中部支部よりご参加頂いた北岡様もどうもありがとうございました。
ご多忙の折、今回のご講演を快諾して頂き遠方よりお越しくださった岡様に改めて感謝の意を示し、今回の報告を締め括らせて頂きます。
(文責:三品)
【出席者(13名)】
井上征四郎(新12回),前田泰昭(新14回),市橋宏(新17回),岡野泰則(新33回),斉藤幸一(新33回),和田昭英(新34回),脇田克也(新36回),髙田隆裕(新37回),澤村健一(新53回),陳鴻(新59回), 三品建吾(新59回),古田武史(新61回), 北岡諭(新36回)