2024年度の応用化学専攻褒賞・奨学金授与式が2025年3月6日木曜日に、西早稲田キャンパス63号館204,205会議室にて開催されました。
褒賞・奨学金の受賞者は、以下のボタンをクリックしてご覧ください

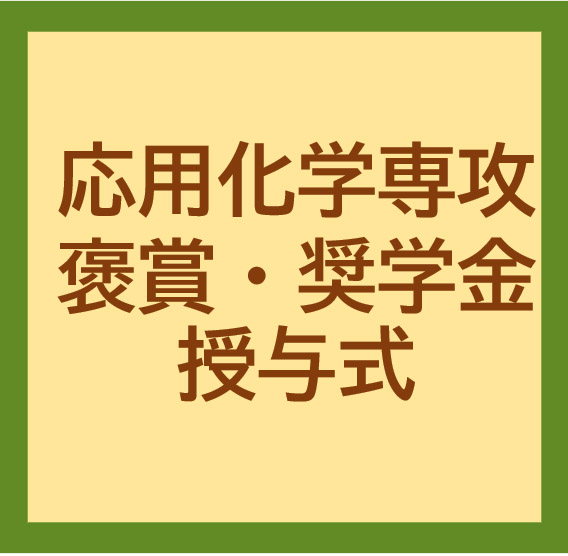

早稲田応用化学会学生委員会は、2025年12月13日、14日に河口湖で縦割り交流合宿を実施しました。
詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

木野邦器教授は昨年4月に古希を迎えられ、2026年3月に早稲田大学を退職されることになりました。先生は、1999年4月1日に早稲田大学に着任されてから27年の長きにわたり本学の教育、研究に尽力されてこられました。
以下の日程で最終講義が予定されています。
日 時:2026年3月21日(土)午後
木野邦器教授最終講義 13:00~15:00(受付開始 12:30)
会 場:早稲田大学 西早稲田キャンパス57号館2階201教室
上記に参加を希望される方は、以下のURLよりGoogleフォームでお申込いただけると幸甚に存じます。
木野邦器教授 最終講義の出欠確認(応化会)
Googleフォーム: https://forms.gle/FC7AwuzXpCX7HFfC8
発起人(学内事務局)
早稲田大学理工学術院
先進理工学部応用化学科
教授 桐村 光太郎
連絡先メールアドレス:kkohtaro@waseda.jp

2026年2月
早稲田応用化学会
会長 下村 啓
平素は早稲田応用化学会の活動にご理解を賜り、ご支援・ご尽力を頂き誠に有り難うございます。厚くお礼申し上げます。
さて、2026年度総会の件につき、ご連絡申し上げます。
開催内容につきまして改めて 「早稲田応用化学会 ホームページ」あるいは「メール配信」等でお知らせいたしますが、まずは開催日のご都合を確保の程宜しくお願いします。
出席の申込は後日「早稲田応用化学会ホームページ」及びメール配信の第二報に申込URLを貼り付けますのでそこからからお願いします。
日時:2026年5月23日(土) 13時30分~18時30分
場所:早稲田大学理工学部西早稲田キャンパス(旧称「大久保キャンパス」※)
※副都心線「西早稲田」駅は出口3でキャンパスと直結しています。
<スケジュール>:
13時30分~14時30分 定期総会(57号館教室を予定)
14時45分~16時15分 先進研究講演会(同上)
16時45分~18時30分 交流会(懇親会)(63号館1階)
会費3,000円(夫婦同伴の場合5,000円)
■定期総会
議題:1)2025年度事業及び会計報告 2)会長の選任 3)2026年度事業計画及び予算案 4)執行部体制 5)規約変更 等
■先進研究講演会「応用化学最前線 - 教員からのメッセージ」プログラム
講師(予定) 高分子化学部門 小柳津 研一 教授
無機合成化学部門 下嶋 敦 教授
触媒化学部門 関根 泰 教授

1月21日、第一回会社施設見学(学生委員)を実施しました。初回となる今回は、ライオン株式会社 平井研究所を訪問させていただきました。
詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2025年12月3日に応化ゼミが開催されました。今回のテーマは「大学院入試(院試)」についてです。 そもそも院試とは何か、推薦入試の仕組み、外部受験の実情などについて、B4の先輩方がご自身の体験を交えて分かりやすく説明してくださいました。優先配属の方、一般入試で進学された方、他大学院へ進まれた方と、それぞれ異なる道を選んだ先輩方のリアルな声を聞くことができました。
詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

2025年11月1日、2日に第72回理工展(@早稲田大学西早稲田キャンパス)が開催されました。応化委員会では「展示」「実験」「屋台」の出店を行いました。多くの方にご来場いただき、両日とも大盛況のうちに終了することができました。
詳しくは、学生委員会HPをご覧ください→こちら

下記の要領で学内講演会が開催されます。
| 演 題 | Transition Metal Dichalcogenides Modified Carbon Nanotubes and Hollow Carbon Spheres for Green Energy Conversion |
| 講 師 | ZHANG, Xiao |
| 所属・資格 | 東北大学 材料科学高等研究所 准教授/ジュニア主任研究者 |
| 日 時 | 2026年3月2日(月) 13:00-14:40 |
| 場 所 | 早稲田大学 西早稲田キャンパス55号館N棟1F第二会議室 |
| 参加方法 | 入場無料、直接会場へお越しください。 |
| 対 象 | 学部生・大学院生、教職員、学外者、一般の方 |
| 主 催 | 早稲田大学先進理工学部 応用化学科 |
| 問合せ先 | 早稲田大学 理工センター 総務課 TEL:03-5286-3000 |
参考:https://www.waseda.jp/fsci/news/2026/01/19/36625/
https://noda.w.waseda.jp/seminar-j.html
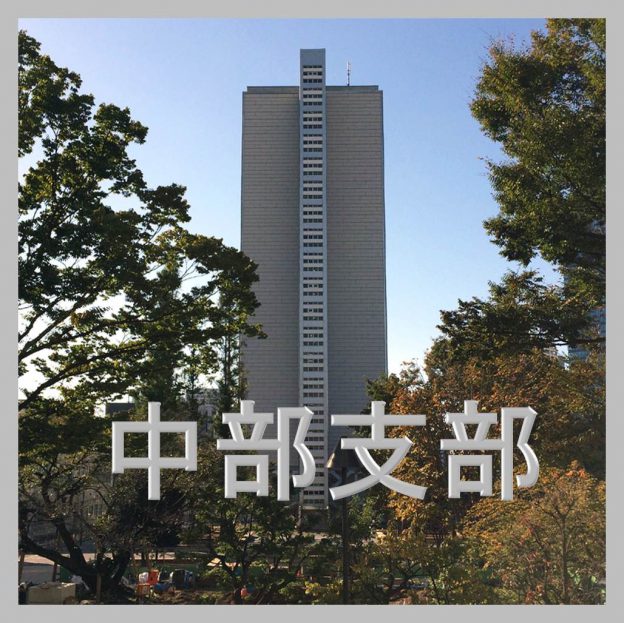
1. 開催日時: 2025年11月29日(土)15:30~17:00
2. 開催場所: ウインクあいち 1309号室
3. 出席者: 20名(オンラインでの出席者を含む)
4. 演者: 細川 誠二郎 准教授
5. 演題: 「天然有機化合物と向き合う:ある合成化学者の思索と挑戦」
6. 要旨:
本講演では、有機合成化学、特に天然物合成の意義・歴史・教育的価値、そして講演者自身が進める最先端研究について体系的に紹介をされた。
天然物合成は、かつては希少天然物の構造決定や量的供給のために不可欠な技術であり、生命現象の理解や医薬品開発の基盤を支えてきた。現在では、量産可能な合成経路を設計し、新反応・新手法を創出する「合成科学」としての側面がより重視されるようになっている。また、天然物は医薬・農薬・生物学研究に広く応用され、植物の成長促進物質、害虫フェロモンを用いた生態系制御など、その利用範囲は多岐にわたる。
教育の観点では、天然物合成は多段階反応を通じて多くの実験操作や反応原理に触れることができ、構造決定能力や問題解決力を育むため、極めて高い教育効果を持つ。意図しない副生成物から新反応が見つかる例も多く、研究と教育の両面を強く刺激する分野である。また、近年AIが合成経路設計に応用され始めているが、ネガティブデータに基づく経験則や想像力、新反応の発案など、人間固有の創造性が依然として不可欠であることも指摘された。
研究紹介では、多様な最先端事例が挙げられた。植物発芽促進物質カリキノライドの3工程での超短工程合成、中分子ポリケチドの新たな合成展開、深海由来の強力な抗がん物質Psymberin類の立体化学の大規模決定(25不斉点中20を確定)、古代生物由来で1億5000万年前の化石に含まれるボロリソクロームの多様化合成、ホウ素中心の光学活性錯体という未踏領域への挑戦などである。さらに、地球初期の生命進化に関与し、UVA〜UVCを吸収するスピトネミンの合成研究も進められており、低刺激性UV吸収剤やバイオマーカーとしての可能性が示された。
天然物合成は科学の基礎から応用までをつなぐ中核的分野であり、希少天然物の供給、生命現象の解明、新薬・新素材創出に不可欠であるとともに、次世代研究者の育成にも重要な役割を果たすことを強調された。
以上
文責:中部支部

12月13~14日に学生主催の縦割り交流会合宿に社会人9名が参加しました。毎年10名前後のOBOGが合宿に参加しています。
寝食を共にする合宿という機会を通じ、学生と社会人の交流を深めました。学生にとっても社会人にとってもお互い良い刺激となった様子がうかがえました。
今年度の若手会の主な活動は全て予定を終えました。今年度の活動で得られたフィードバックを参考に、来年度も社会人向けの企画および学生と社会人の交流を目的とした企画をいずれも実施していきます。
社会人で若手会の活動に興味がある方は、今後の活動案内をお送りさせていただきますので、お気軽に以下のアンケートフォームにご入力いただけると幸いです。
若手会を一緒に盛り上げていきましょう。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU85i8JLGcpTRwtVI9smi2FBaA2PjJh_hMbnzsRirp2rVK6A/viewform
(参考)25年度の若手会活動実績
(文責:大山)