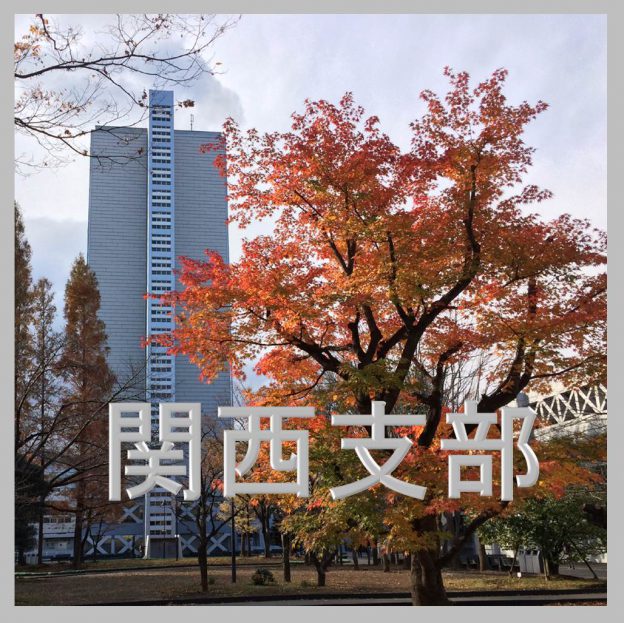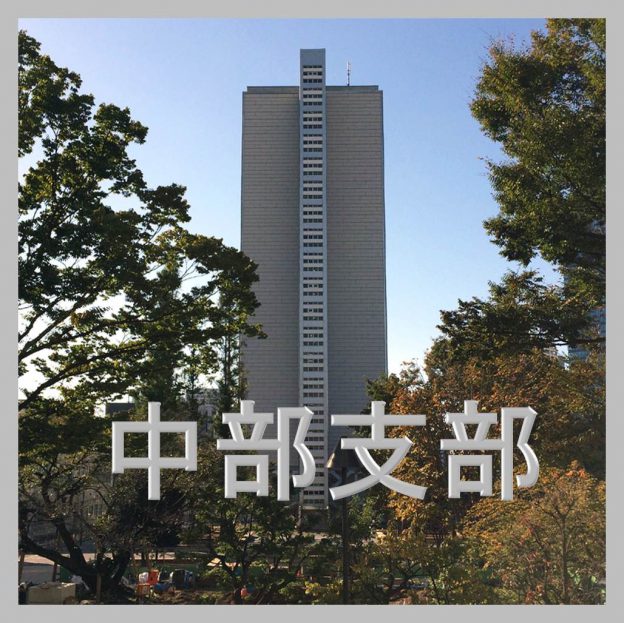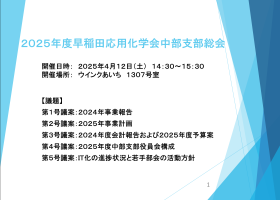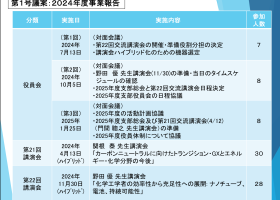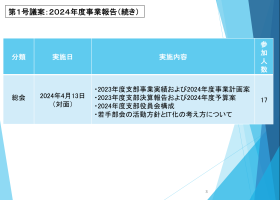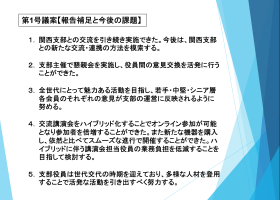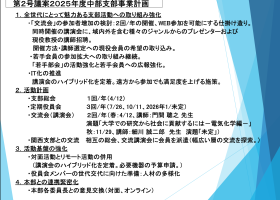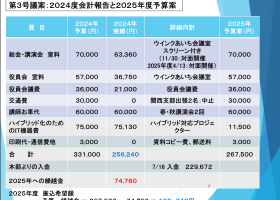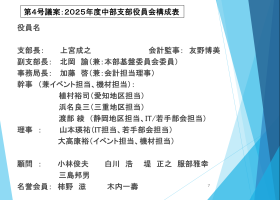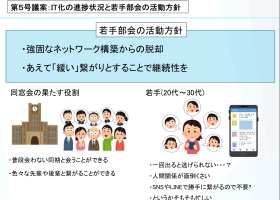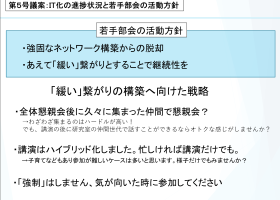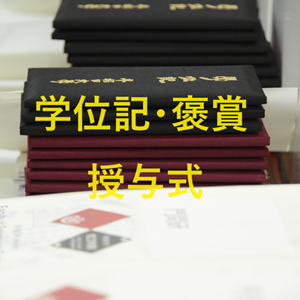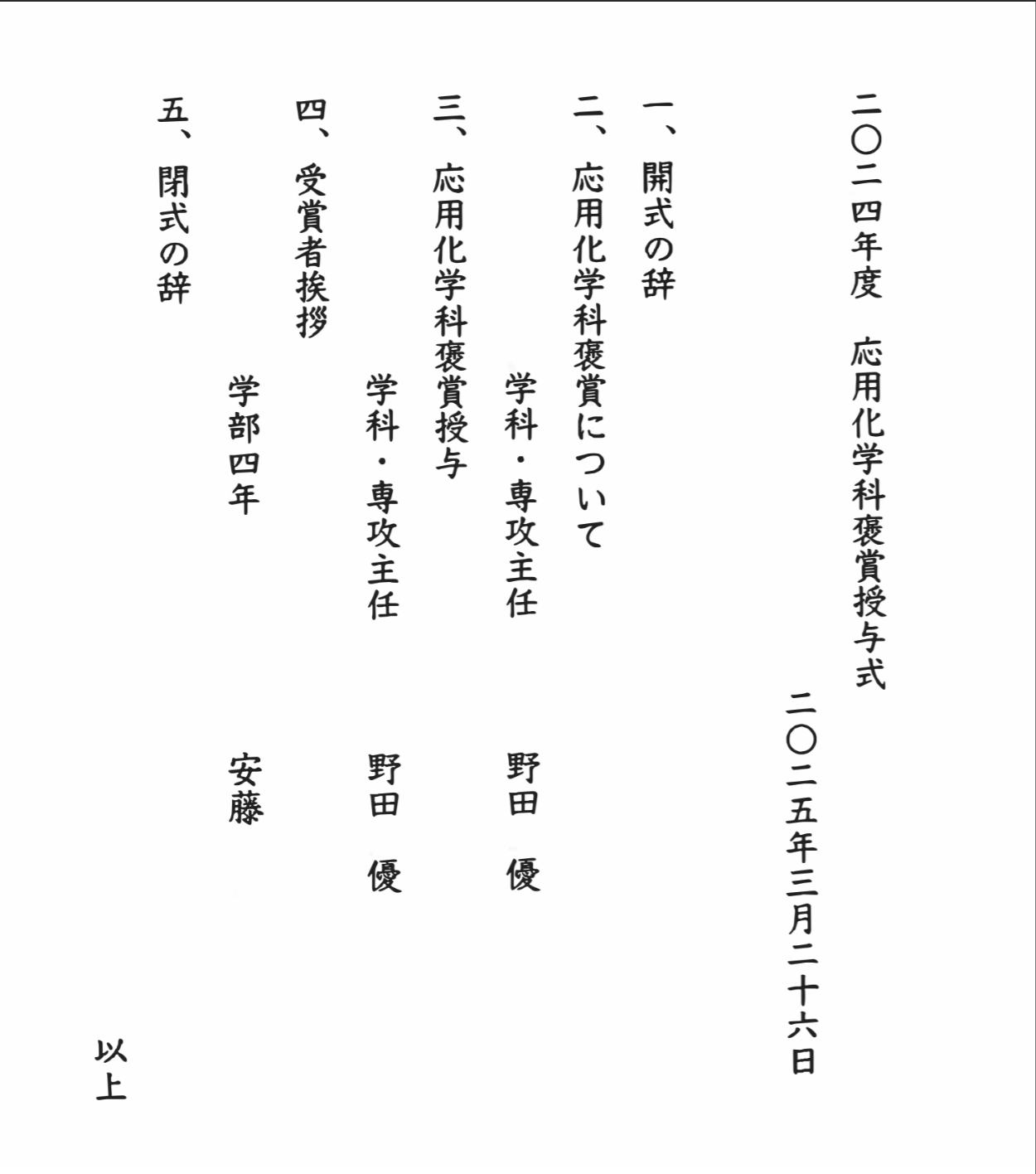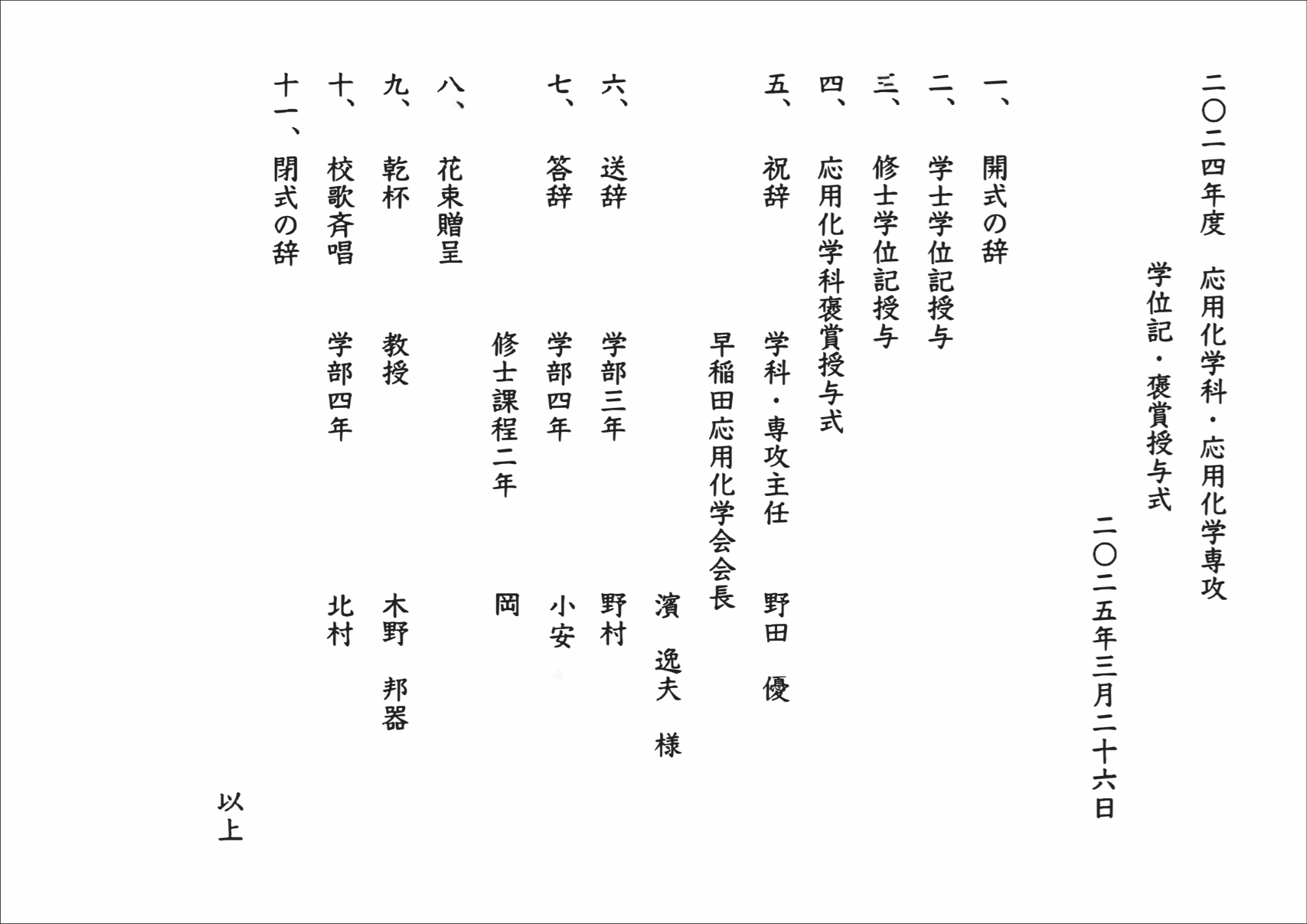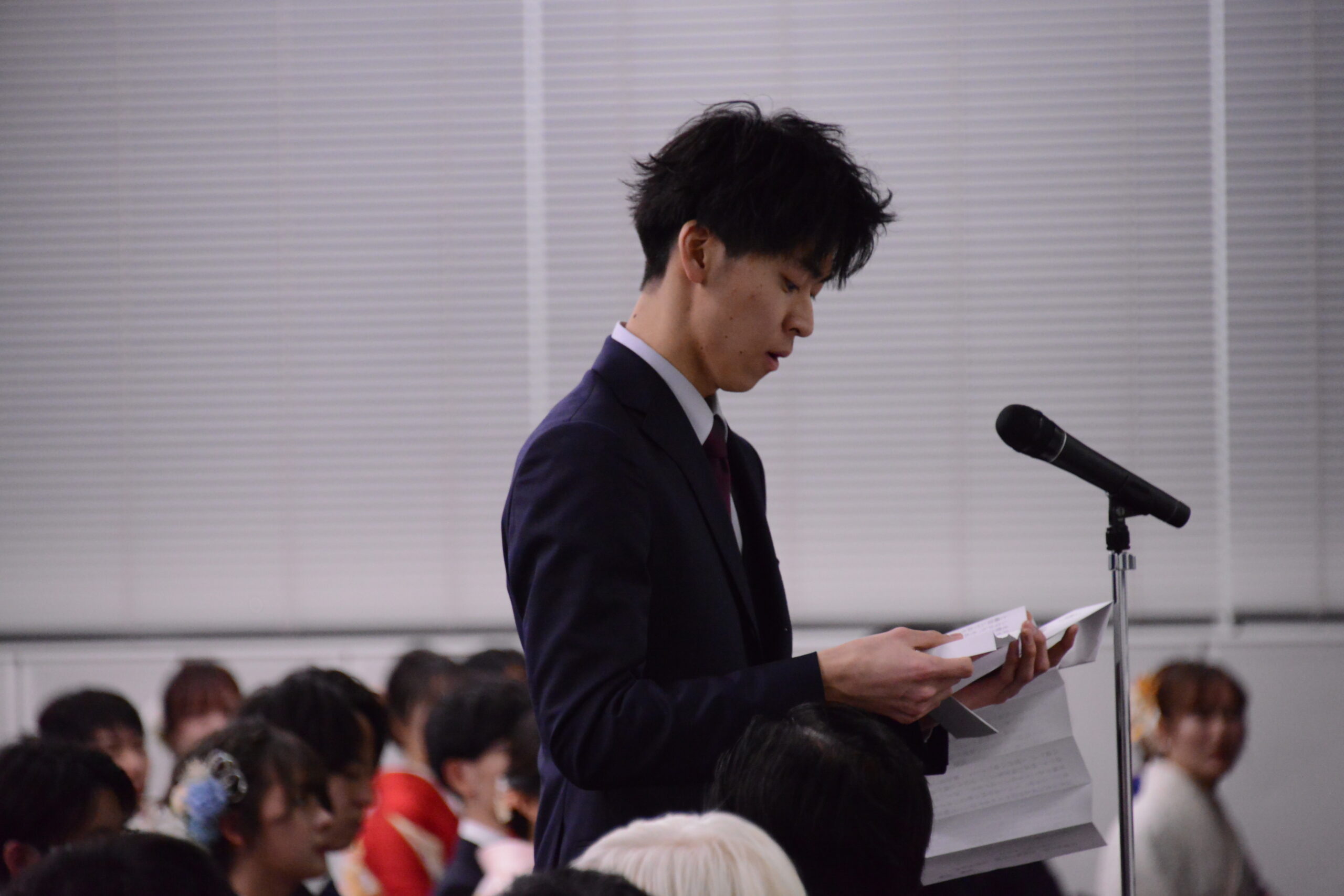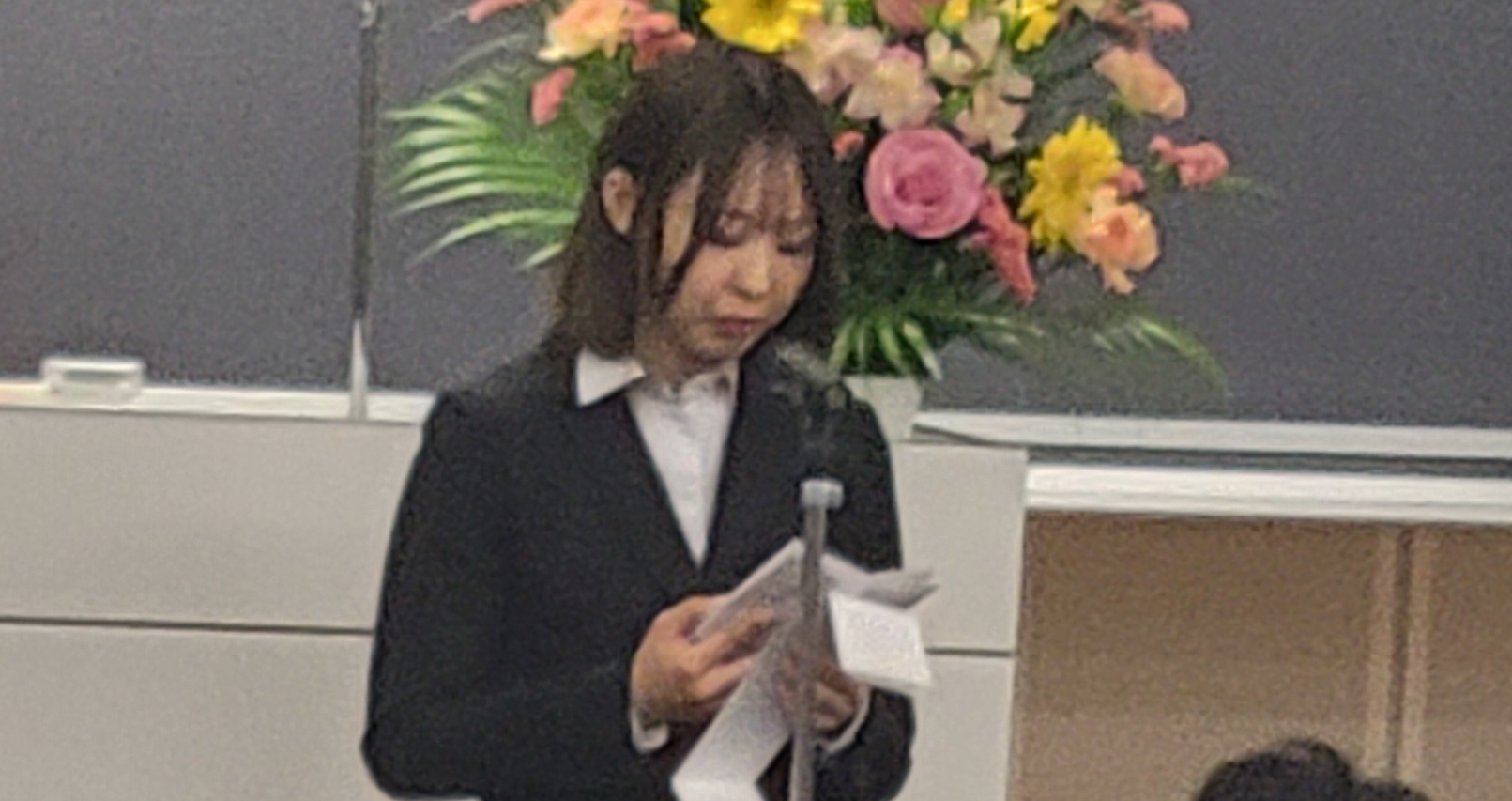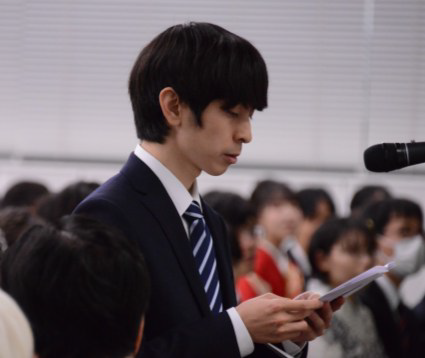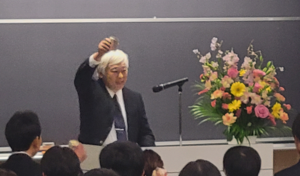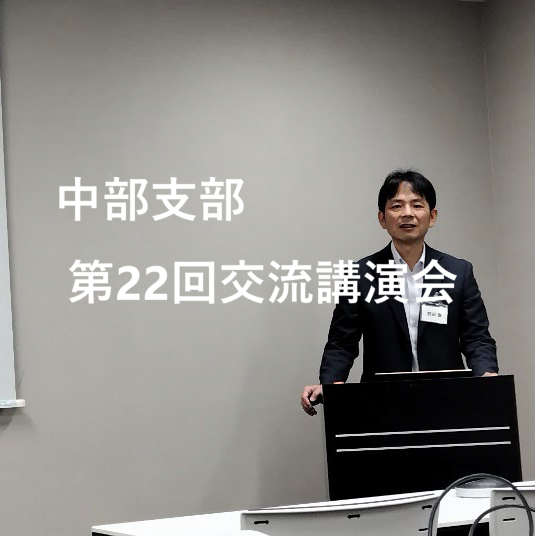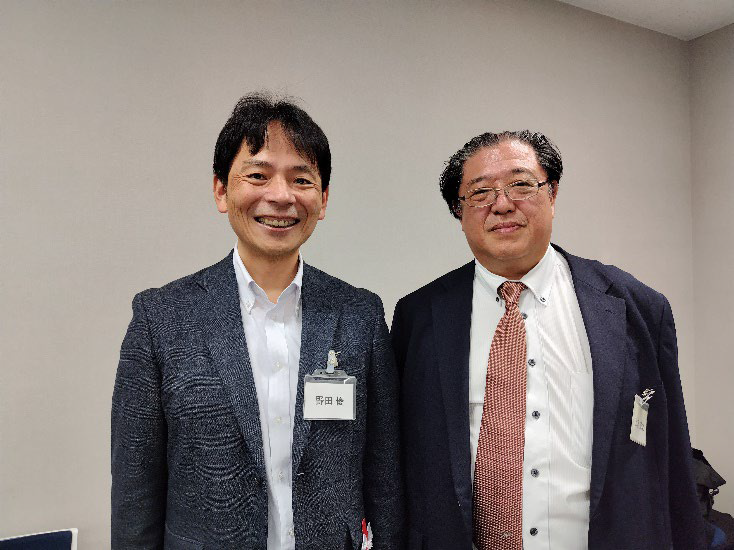2025年度早桜会総会を2025年4月26日(土)にWEB形式(Zoom)にて開催し、その後講演会を中央電気倶楽部にて実施いたしました。今回の講師には岡野泰則先生による、「ロートル教授の世界漫遊記-やっぱり日本がサイコーだったー」という演題でご講演して頂きました。
【講師】岡野泰則氏 (大阪大学名誉教授、新33回)
【概要】
2020年以降コロナの影響で様々な活動が制限されていました。その反動で2023年以降、怒涛の国際学会ラッシュとなり、2023年-2024年の2年間で岡野先生が多くの国を学会でご訪問されたので、その時に体験されたことや所感等を色々とお話しして頂きました。
2023年はアルゼンチン、イタリア、南アフリカ共和国、ベトナム、韓国にご出張されました。アルゼンチン、南アフリカ共和国は通常なかなか訪れない国ですが、実際に訪れてみるとやはり日本と比べて安全に気を配る必要があったそうで、街中の移動には基本的にUberで移動されていたようです。しかし良い面も多く、アルゼンチンは食事も美味しく南米のパリと呼ばれるほど街並みが綺麗であり、南アフリカ共和国は喜望峰やテーブルマウンテンなどの観光地はとても良い所だったようです。イタリアは学会の開催地がナポリであり、大変綺麗な港町で食事も美味しく、人々は親切だったようです。スリに注意は必要なものの、さほど治安は悪くなかったようですが、円安による物価高であり、またあまりにも観光地化され過ぎてしまって何かとチップを要求される、といった負の側面もあったようです。ベトナムはホーチミン、韓国はソウルを訪れており、どちらも大都市なので英語も通じるし、日本からのアクセスも良く、あまり不自由は無かったようです。ホーチミンは物価も安く食事も美味しい一方で、バイク(3人乗りが当たり前!!)が多く、大渋滞で空気も悪いといった面もあったようです。これは私の私見ですが、良くも悪くも活気に溢れた都市、ということなのかと思います。ソウルでは高麗大学の学生と会い、色々とお話をされたようですが、韓国では博士課程の学生は学生というより研究者であり、30歳以上が当たり前で家庭持ちも普通、と日本とは大きく異なるとのことです。韓国では博士を取得しているか否かでその後の待遇も大きく異なり、苦労をしてでも博士を取得する価値があるし、採用する側もそれだけの給料を払ってでも雇うだけの価値を博士号取得者が持っている、とのことです。
2024年はポルトガル、シンガポール、ポーランド、ドイツ、インドネシアにご出張されました。ポルトガルではポルトという都市が学会の場所だったとのことで、正直私は初めて聞く都市でした。魔女の宅急便のモデルになるような綺麗な街並みであり、治安も良かったようです。比較的地方である為ヨーロッパの中では物価も安く、食べ物も美味しく、とても楽しい場所で是非また訪れたいとのことでした。シンガポールは安全で衛生的で日本からも近いし、MRSやバスでどこでも行けて利便性が良かったようです。そして、シンガポールの空港は国際的なハブ空港として発達しており、非常に機能的に街が設計されているようです。食事も美味しく、3つの異なる文化(中国系、アラブ系、インド系)が混在する興味深い街とのことでした。ただし物価は高く、とにかく暑いとのことで、必ずしも暮らしやすくはないのかもしれません。ポーランドではワルシャワが学会の場所で、美しい街並みで安全な場所だったようです。というのも、様々な歴史的な背景から移民を徹底的に排除していることが治安が良い要因の1つとのことです。また物価は安いけれども食事は美味しくなかったようです。宿泊したホテルが16世紀のお城でエアコンも冷蔵庫も無かったようで、中々日本では考えられないなと個人的には思いました。ある意味ポーランドと対照的なのが、次にご出張されたドイツ(ミュンヘン、ベルリン)のようです。25年前に岡野先生がご訪問された時は、ベルリンは未だに東西格差が残り、ミュンヘンは日本でいう京都のような伝統的な街だったようですが、現在は東ベルリンは大都市へと変貌を遂げ、一方で西ベルリンは25年前とあまり変わっていなかったようです。ベルリン市内に広大な移民街があり、リトルイスタンブールと呼ばれ、名物はケバブ。ベルリン空港では荷物の受け取りに2時間待たされ、新幹線は30分遅れ。我々のイメージする厳格なドイツとはだいぶ実態は異なるようです。ミュンヘンも市街地は昔と変わらず安全な街並みですが、シラー通りと呼ばれる移民街は英語すら通じず、治安も良くなかったようです。移民問題はキレイごとでは片付けられないというのが実際に現地を訪れた岡野先生の所感とのことで、日本も他人事では済まされないと私も思います。最後にご出張されたのがインドネシアのバリ島で、いつもより多数の日本人が参加しており、比較的日本語も通じる環境で、日本がまだ元気だった頃の海外の感じが残っていたようです。海は綺麗で物価も安く、比較的日本からも行きやすい、というように良い所ですが、学会では日本勢は苦戦していたようです。日本からは比較的多くの人が参加していたものの、賞を獲ったのは北海道大学のみで発表者はベトナム人、というように日本にいる日本人の受賞者は0人。近年はASEANのレベルが向上し、特にエネルギーや環境の分野に力を入れていて、発表のレベルも高いようです。
というように様々な国を訪れた結果、安全で経済も安定しており、サービスの質が高く、公共交通の時間が正確で、多種多様な食事が食べられて、清潔で無料のトイレがどこにでもある日本、というのはやはり素晴らしいと実感されたとのことです。一方で課題もあります。当日の質疑応答の中でも議論が盛り上がった内容ですが、若者が効率化ばかりを求め、とにかくリスクや未知のことを恐れる傾向にある、ということです。もちろん全員ではないですし、チャレンジ精神に溢れた若者もいます。しかし、昔はある一定以上のレベルを目指す若者は、ほぼ100%の人がチャレンジ精神旺盛な人達だったのに対して現在はだいぶ様子が変わってきているようです。
しかし私は思います。子供や若者が失敗するのは当たり前です。だからどんどん失敗して、そこから学べば良いだけです。岡野先生が多くの国を訪れて感じられたことからも分かるように、どの国もみな違いますし、考え方もバラバラです。しかしどこの国も国として成り立っており、学会を誘致出来ている訳です。そう考えると別に正解は1つではなく、それぞれの価値観の数だけ正解があるとも思います。もちろん誰がどう考えても失敗だ、というケースもありますが、若いうちならばいくらでもやり直しはききます。私自身たいそうなことを言えるような身分でもないですが、個人的に思うことは、’’正解することばかりにとらわれなくても良いのではないか’’ということです。
長くなってしまいましたが、通常ではなかなか出来ない貴重な経験についてご講演して下さった岡野先生に改めて感謝の意を示し、報告を締め括りたいと思います。
(文責:三品)
【出席者(13名)】
井上征四郎(新12回),前田泰昭(新14回),市橋宏(新17回),田中航次(新17回),岡野泰則(新33回),斉藤幸一(新33回),和田昭英(新34回),中野哲也(新37回),髙田隆裕(新37回),澤村健一(新53回),三品建吾(新59回),古田武史(新61回),岡義久(新33回)