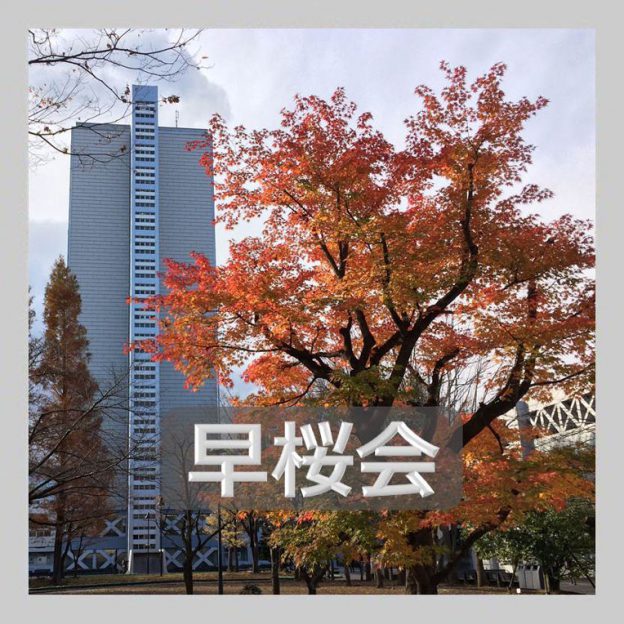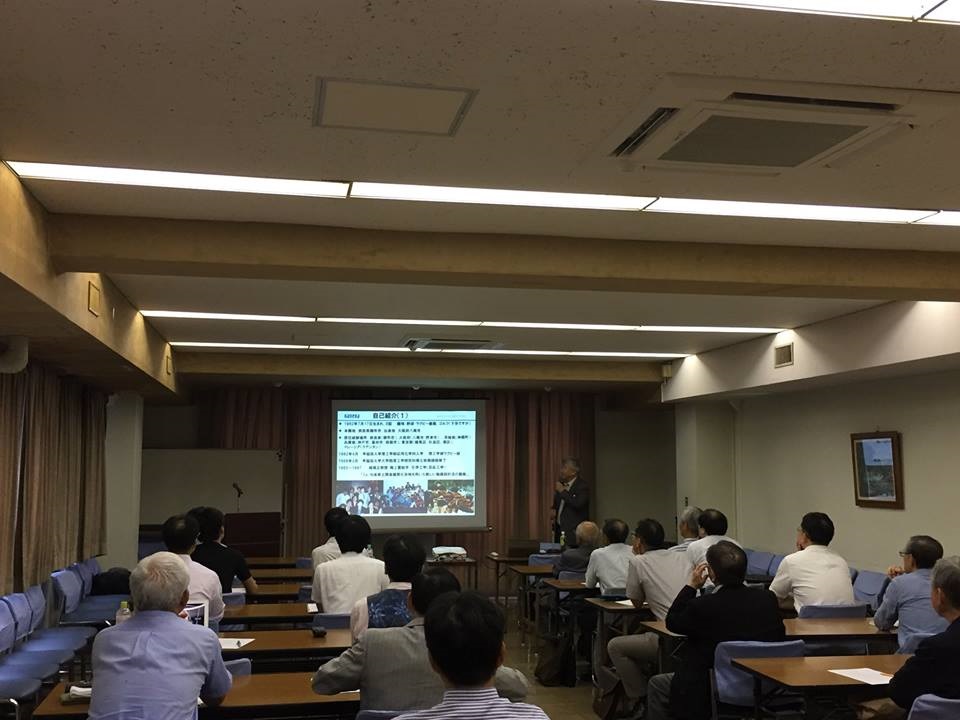第10回早桜会講演会を2018年9月22日(土)に大阪・中央電気倶楽部で開催しました。
演者は、古川直樹氏(新36回 城塚研 ㈱カネカ 常務理事R&D企画部長)にお願いし、企業の中での研究者・技術者のあるべき姿、心構え、考え方について、特に若手研究者・技術者向けにお話しいただきました。
演者は、若い新入社員時代からいくつもの社内プロジェクトに参加する機会があり、特に社を挙げての大きなプロジェクトに参加できたときは、自らの成長を確信できるような感動があったそうです。
企業研究者・技術者は、できれば学位を取得し、学会等で大学の先生や社外の研究者・技術者と交流し、人脈と知識の幅を広めていってほしい。 語学、特に英語については、ある程度堪能であることはこれからの時代は必須であり、自分なりの努力を続けて欲しい。
会議等の場で、自分が正しいと考えている事象については、たとえ言いにくいことであっても勇気をもって主張しなければならない。 他にも多数参加してくれた若手からいろいろな質問が出され、一つ一つ丁寧に答えていただきました。
講演会には、来阪中の応化会西出会長にもご出席いただきました。
講演終了後は、いつもの特別食堂に席を移し、和やかな歓談の場が持たれました。西出会長には、エールの音頭もとっていただき、フレーフレー応化会の叫びが大阪でこだましました。
出席者
古川直樹(新36回)、西出宏之(新20回)、津田實(新7回)、井上征四郎(新12回)、市橋宏(新17回)、井上昭夫(新17回)、田中航次(新17回)、岡野泰則(新33回)、斎藤幸一(新33回)、牧芳彦(新34回)、和田昭英(新34回)、原敬(新36回)、高田隆裕(新37回)、中野哲也(新37回)、髙島圭介(新48回)、荒井直樹(新50回)、遠藤文子(新50回)、數田昭典(新51回)、澤村健一(新53回)、吉原秀輔(新55回)、陳鴻(新59回)、猪村直子(新60回)、古山大貴(新65回)、前田傑(新65回)、御手洗健太(新65回)
以上 25名
(文責 田中)