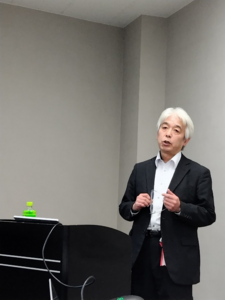開催日時: 2025年4月12日(土)15:30-17:00
開催場所: ウインクあいち(愛知県産業労働センター)1307号室
出席者: 31名(オンラインでの出席者9名)
演者: 門間 聰之先生
演題: 「大学での研究から社会に貢献するには -電気化学編-」
要旨:
●初めに、司会の渡部幹事より門間先生のご略歴が紹介されました。続けて、門間先生より本日のご講演概要についてご説明があり、本題に入られました。
- 電気化学は、社会実装という観点から、非常に身近な化学です。近年では電気自動車やドローンに蓄電池が用いられていますし、古くから、めっき、乾電池、あるいはトタンといった電気化学を利用して作られた部材や、電気化学を利用したデバイスが身近にありました。
- 私の研究室では、電気化学センサーや蓄電デバイスなどの応用を目的とした材料やデバイスの研究、また、その評価のための測定法の開発を行なってきていますが、分析手法の開発を含めて、何より研究が楽しいことが重要です。大学教授は研究テーマを自由に選べることも大切ですが、本日の講演では、その一端を紹介したいと思います。
- 将来の電池用電極を改良するためには、その反応場の評価が重要です。このために、当時としては新しい測定技術を開発し、電極反応の評価を行なってきています。その際に知った、より良い反応場の知見を基に、理想的な材料に思いを巡らし、新しい材料の設計から合成へと展開しました。頭で想像していた特性以上のデータが出てきて、楽しい研究となりました。
●電気化学とは:
- 化学反応:一種またはそれ以上の物質が、それ自身あるいは相互に電子の組み換えを行ない、元と異なる物質を生成する変化[理化学辞典]。化学反応と電子のやり取りが、酸化還元反応を起こす。
- 電気化学:反応場に電極を挿入し、電子のやり取りを反応物と電極間とで行なう。電極を外部の回路に接続することで、反応の制御と測定が可能となる。
●何ができるのか:
- 反応させたい物を選ぶことで、選択的に反応できます。Σ電気量=反応量といえます。使用するデバイスで「物づくり」が可能です。電気化学センサーは電池がメインで、アプリケーションが豊富です。
- 電気化学反応を利用するデバイス
-
電気化学反応を利用した物づくり
化学状態(特定物質の酸化状態や濃度など)
⇔電位・電流といった電気信号へ変換 ・・電気化学センサー
高い化学エネルギー状態(酸化状態や濃度など)
⇔電位・電流といった電力へ変換 ・・燃料電池、電池
電気エネルギーから化学エネルギーへの直接変換
⇔電力を使って合成、物づくり ・・精錬、食塩電解、水素/酸素ガス製造、めっき
●LiBの特徴:
-
高いエネルギー密度
– 高い重量エネルギー密度・・電池の軽量化可能
– 高い体積エネルギー密度・・電池の小型化可能
– ロッキングチェアー型作動・・電解液は少量でOK
- 塗布工程を基本として、初回充電で完了する電池形成プロセス・・製造が安全で容易
- LiB2次電池の構成:その昔、フロッピーディスクがあり、花王が参入しました。何故、花王ができたのでしょうか? 答えは、スラリーや固体をきれいに分散させる技術=花王が持つ「界面活性剤技術」の適用です。しかし、塗布して乾燥させるだけで、どこの誰でも真似ができる技術なので他国へ流出しました。
- 「初回充電で完了する」がキーワードでしたが、「取り扱いし易い」ことは、「真似され易い」の意味でした。
●SEI[Solid Electrolyte Interface]のこと:
- 負極と電解液の界面に、主に充電時に形成される層状の被膜が活性物質を保護します。私の研究室では、ある方法で倍以上、また約10倍の効果を得ました。すなわち、材料を1/10に減らす軽量化が可能になりました。微粉化するなら最初から、電子レベルでSEIになるように混合させる方法も開発しました。しかし、良い物を開発しても、世の中が受け入れないこともあります。軽量化の結果、充放電が20年OKとなると、LiBを新しく作ることは不要となり、製造工場が停止することを意味します。
●直接めっき法で活物質形成:
- 活物質[SiCl4]を形成するためには、水の無いドライルームが必要です。SiCl4は水と反応するとHClが発生します。そのため、特殊すぎる製造環境が必要ですが、特性が良くても大量生産となると、ドライルームだけで数億円かかります。その他にも欠点があり、数年で止めました。
- 硫黄電池:LiS電池[Li2Sx(4<S<8)]が期待されています。日本は大量に原油を輸入するので、石油精製の脱硫により硫黄が大量に得られることで、その活用に関する技術開発が進んでいます。
- Li2S8は「溶媒に溶け易い」という問題があり、溶けにくい溶媒、溶けにくくする膜を提案しました。具体的には、ポリピロールをコーティングした正極構造で充放電が上手く回ることが分かりました。
- 電解液ではなくイオン交換膜で解決させるため、理想は電子が流れる薄膜を細孔に塗ることですが、導電性のあるポリピロールとアセトンを使いました。アセトンは‐70℃でも固体にならず、細孔にピロールが入るのは、室温へ温度上昇する状態で化学反応が起こる、と信じています。これまでの実験で「ドライアイス-アセトンは凍らない」ということ、また「拡散」も含めて、昔に習った知見が役立ちました。
●LiBの解析:
- 2次電池の反応素過程を知りたい・・診断をしたい。しかし、電池を開封すると壊れて、元に戻りません。
- 電気化学インピーダンス法:対象とする電極に微小な正弦波交流を与え,その伝達関数としてインピーダンスを求めることにより電極反応機構などを解析する非定常測定法の一つですが、交流電流は周波数を変えられます。高周波でも電子は付いてくるので、反応の素過程を分離できます。この技術開発は「測定法としての社会実装」を果たしたと思います。
- 電池メーカーから製品の提供が得られなくなり、自分たちで電池の製作を行なったことも、その後の開発に役立つこととなりました。
●まとめ:
- 電気化学デバイス:電気化学の反応場まで反応が進行するためのリード線や電極/電解液界面といった電気化学測定に必要なパーツは揃っています。
- 如何に「反応場の情報を取り出せるのか?」を工夫することで、有益な情報を得ることも可能になる・・ことがあります。
- 得られた情報を上手に展開することで、新しい電極の形成も可能となる・・ことがあります。
- 研究に必要な設備や装置、また電池自体を手配できなくなり、自前で、自分の研究室で製作するようになったので、大学やアカデミックとしては企業並みの設備を有しています。
- 研究結果から派生した「物」は、実態として社会貢献していると自負します。
- 高くても、良いから買ってくれる「物」を開発することが「社会実装」に繋がります。
- 分析手法からフィードバックすること。これも、一つのキーポイントだと思います。
●Q&A
Q1: LiBの再使用には活性化が必要だと思いますが、完全放電すると元に戻りませんか?
A: ある程度は復活するはずですが、劣化はします。想像ですが、元に戻らせない回路があるのか、安全性からの配慮なのかもしれません。
Q2: 実験の際に、複雑系材料のインピーダンスを解析することが難しく、データベースや組成などで整理はできますか?
A: 正極と負極のインピーダンスを個別に検討します。正極の成分、負極の成分などで整理します。
Q3: 変なインダクタンスが見られた場合、良く分からないものが出てきた場合、どのように解釈すれば良いですか?
A: 機器に由来するのでは? と、疑います。電気化学系の反応場を模したダミーセルで確認します。
Q4: 電池の寿命はバラつきますか? バラつかせている支配因子があれば教えてください。
A: 同じ電流電圧であれば、バラつかないはずです。実装化において100セルを直列させていますが、寿命をバラつかせてはいけません。同じ環境で充電しており、バラついてしまっては、今の市場では使えません。温度コントロールがどこまでできているかがキーポイントであると思われます。
Q5: Chat GPT について、大学では使用禁止ですか?
A: 基本的に不可ですが、実際にどのように使っているかは分かりません。Chat GPTが本当に便利なのか? 作文能力は低下しますし、論文などが日本語になりません。
質問が続きましたが、懇親会の場でお願いすることとなりました。
参考資料(ご略歴等:早稲田大学研究者データベース)
https://w-rdb.waseda.jp/html/100000400_ja.html
以上
(文責 浜名)