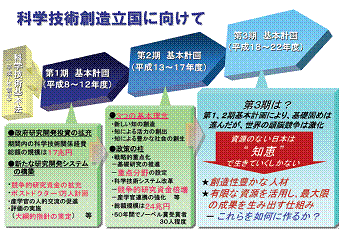2010年度定期総会・講演会要旨(木村茂行氏)
演題:科学技術政策による未来開拓戦略
講師: (社) 未踏科学技術協会理事長 木村茂行氏(新制13回卒)
- はじめに
- 1970年に科学技術庁無機材質研究所に研究員として 入所し、数年後の37歳で部長職を拝命したとき、 「国家公務員の部長職以上は国家意思の形成に関与する」 と聞いて愕然とした。国立研究機関の使命とは何、 国家意思の形成とはどう決まるか、自分の役割は何か、 など様々な疑問が黒雲のように湧き起こった。 この日以来、科学技術政策というものが意識から離れな くなった。甲斐性なしの身で必死になって研究所の運営 を考え、科学技術庁本庁の意向を理解しようと努めた。 本日の話題は、そのような一研究者が不慣れなことを考え、 それを消化しようと努めつつ、最後は国立研究所一つを 任されて政治改革の嵐に巻き込まれ、中途半端な達成感と 共に退職をした中で見つめた日本の科学技術政策の変遷で ある。
- 超党派満場一致で成立した科学技術基本法
- 1995年10月31日に衆議院を、翌日参議院を通過した科学技術基本法は特徴的な政治背景の中で発効した。米国を中心に外国から基礎研究ただ乗りを指摘され、ジャパンバッシングや日本市場の閉鎖性批判が展開される中、1990年にバブルが破裂、1992年に戦後初めての地価の値下がり、1993年の就職氷河期をへて、後に言われた「失われた10年」が姿を現し始めた時期である。「科学技術創造立国」の名の下に議員立法がなされたこの基本法には反対票がなかった。祈るような気持での「未来開拓」への期待があった。最も大きな期待は、政策的に誘導した科学技術の進展によって新産業の創出が可能となり、産業の国際競争力が増すのではないかという点にあった。
- 科学技術基本法のポイント
- 科学技術基本法は国の科学技術政策のあり方を規定したものだが、重要な点は、国や地方公共団体の科学技術振興についての責務を明確化したことと、科学技術基本計画を作成しなくてはならない、としたことである。この結果、周知の科学技術基本計画が5年毎に改訂されることになった。なお、基本法とは、憲法と個別法との間をつなぐものとして、憲法の理念を具体化する役割を果たすもの、とされている。
- 「科学技術省構想」の挫折と第1期科学技術基本計画
- 科学技術基本計画の第1期は1996年4月から2000年の3月までであるが、その計画の作成に5ヶ月弱しか時間がなかった。作業は当時の科学技術会議の采配による、というものであったが、実際は科学技術会議の事務局だった科学技術庁が務めた。科学技術庁は折から計画が進められていた行政改革の中で、科学技術省に昇格することを目指していたふしがあり、科学技術基本法制定をその追い風にするはずであったが、「もんじゅ」事故と、前後しての原子炉の事故で、当時の橋本首相が文部省との統合を決めた。
第1期科学技術計画は、ポスドク1万人計画、優秀な研究マネージャー等の養成・確保、研究支援者の確保、女性の研究者等への採用機会確保、研究開発業務を労働者派遣事業が可能な業務に追加、などの目玉があったが、大きかったのは「システム整備」の名で進めた制度改革である。この計画には、老朽施設の改修から海外人材の大幅受け入れまで、知財整備から任期付任用まで、アカウンタビリティから競争的資金拡充まで、何でも盛り込んだ感があり、国立私立を問わずあらゆる研究開発機関が変化の渦に巻き込まれた。
- 第1期計画の結果と第2期計画
- 第1期の5年間で目標通り17兆円を使い、ポスドク1万人計画は4年で達成したが任用終了後の身の振り方に問題を残し、兼業緩和も行ったが人材流動は不十分、研究評価実施は進展したが結果の資源配分・処遇への反映は不十分、評価のあり方にも問題を残した。公的機関からの特許申請は増加、産学連携も進展、国立大学等の敷地内での共同研究施設も整備が進んだ。施設の老朽化・狭隘化問題の解消はあまり進まず、明確な研究開発の成果はまだ見えず、本格的な科学技術創造は途についたばかり、というのが第1期終了時の印象と言えるかもしれない。一方で、大学や国研など政策展開の現場では多大の、しかも効率的とは言いがたい努力を強いられた面もあった。 第2期計画は、戦後最大の行政改革といわれた省庁再編の直後から進められたが、同時に従来の科学技術会議は廃止、新たに内閣府に総合科学技術会議が設置された。その総合科学技術会議の主導で「選択と集中」が図られ、重点4分野とその他の4分野が設定された。2000〜2002年に4人の日本人ノーベル賞受賞があり、50年間でノーベル賞受賞30人目標も掲げた。さらに科学技術システム改革も鋭意進めることとなり、国際的な人材育成競争を意識して、国際化推進も強調された。人頭研究費より競争的資金が重要、ということで、競争的資金倍増を目指した。計画当初、国立研究所が独立行政法人に衣替えしたが、政府機関削減に見せるための政治的役割も果たした。
- 第2期計画の結果と第3期計画
- 2004年には、急転直下の印象で国立大学の法人化が断行され、職員の非公務員化というおまけもついた。第2期での総額24兆円は未達成、重点4分野への集中度は38%から46%へ向上、競争的資金は倍増しなかったが全科学技術予算の8%から13%になり、プログラム・オフィサーの活躍が始まり、間接経費30%も部分的だが実現した。任期付研究者が増え、評価の取組みが進み、技術移転機関(TLO)による移転実績も増加し、大学発ベンチャーは1000社を越え、地域における科学技術振興も充実した。が、老朽施設の改善は遅れた。
期間中のGDPは、平均3.5% 成長と目されたが、2%以下で低迷し、失業者が漸増する中で、科学技術創造立国はどんな有難みを発揮しているのか、予算のばらまきではないか、との批判が噴出した。それに応える意味もあり、第3期では「成果還元型科学技術」と「人からモノへ」の掛け声と共に、3つの理念、6つの国家目標の下、政策の具体化を進めた。重点4分野とその他の分野は、重点推進4分野と推進4分野になり、分野別推進戦略を策定、また重点投資対象として「戦略重点科学技術」を選定し、その中で「国家基幹技術」を精選した。システム改革では、小泉内閣の時代でもあり、女性研究者を25%にする目標、イノベーション創出の仕組み作り、アジアを主な対象にした国際政策展開、などを目指した。一方で、研究費使用に不祥事が発生した経緯もあり、国民の目線を意識したアウトリーチ活動の展開を図った。総額目標は、紆余曲折の末、25兆円とされた。
- 第3期計画の結果と第4期計画
- 2008年に新たに4人のノーベル賞受賞者があり、意気軒昂の一面はあったが、第4年目の2009年末の段階で17.3兆円、総額25兆円は達成不能となった。2008年の論文数は米国、中国に次いで3位だが、被引用数では米、英、独、加、仏に次いで6位。京都大の山中教授のiPS細胞と東工大の細野教授の鉄系超伝導体が基礎研究成果の事例とされた。戦略重点科学技術では、高効率太陽光発電や水素エネルギー利用技術、組み込みソフトウェア技術や電子デバイス技術が産業の国際競争力強化に、また、知能ロボット技術や再生医療技術が健康な社会の構築に、希少資源対策技術やグリーン科学技術(DNA組み換え微生物利用、エネルギー生産、新触媒)が日本と世界の安全保障に、それぞれ寄与が大な事例とされている。大学等の競争力強化のためにグローバルCOE、世界トップレベル研究拠点形成(WPI)、先端融合領域イノベーション創出拠点の形成の各プログラムを実施。産学連携によるイノベーション創出の取組としては、液晶やプラズマに代わる次世代ディスプレイとして期待される有機ELディスプレイを開発・初めて実用化した事例、また完全養殖クロマグロの産業化などの事例がある。
第4期計画は、2011年度からの実施を目指す。2009年12月の新政権の新成長戦略に基づき、成長を牽引するグリーン・イノベーションとライフ・イノベーションを2つの柱に掲げ、細部を作り上げる計画になっているが、まだ作成中である。
- 期待と現実
- グローバル化が進んだ現状では、研究成果が国内の産業競争力を育てるとは限らない。素晴らしい成果が出ても、それを商業化するのが外国企業であったり、日本の企業でも実施は海外であったりする。国内の雇用創出に直接繋げる仕組みが作れない。政策推進の財務基盤が我々の税金であることに当惑を感じる。
科学技術基本計画に基づく政策には、様々なセクターの人々が、それぞれの思惑で群がった。大学や公的研究機関の人々は、これを生き残りの機会にしたいと考えた。産業人は次世代製品開発への助成の機会を見出したかった。国民一般は、国内産業の隆盛と雇用の機会拡充を期待した。政治家は活躍の場を見出し、集票力強化に繋げたかった。もっとも割の悪かった国民一般が乗り切れなかった。それが「なぜ世界で二番ではいけないのですか」という事業仕分けの一言に拍手を送った。今後は国民の目線が無視できない。間もなく第4期基本計画に対するパブコメ募集が行われる。意見多数が望まれる。
(文責:交流委員会 中川善行、井上凱夫)